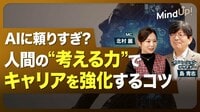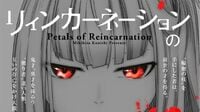顧問強制しない米国に学ぶ「部活動改革」のヒント 対価や専門管理職で公平さや負担軽減を図る
学校外から指導者を雇用するに当たっては、適任者であるかを見極めるため、州の教育に関する法に従って、各州の高校体育協会が外部からの指導者について資格を定めている。全米スポーツ・体育協会(National Association for Sport and Physical Education)(※)の2008年の調査によると、全体の約4割の州で、指導者に教員免許を求めている。米国の学校運動部でも、競技指導に長けていることよりも、教育者としての資質が優先されているといえるだろう。
※現在は、体育や健康に関する全米基準策定などを行う米国の非営利組織であるSociety of Health and Physical Educators(保健体育教育者協会)に統合
しかし、教員免許を条件にすると応募者が限られ、指導者不足を補えないという現実があり、定められた指導者資格を持っていれば、教員免許の代わりと認めるなど条件を緩和している州も少なくない。
実際に外部からの指導者の採用を決める手続きはどうなっているのか。この重要な仕事を担っているのが「アスレチックディレクター」である。学校の運動部全体をマネジメントする役職だ。校長下の管理職であり、筆者が取材した学校では副校長や体育科主任と兼任しているところがあった。
州の高校体育協会の規則を理解し、競技全般に関する知識を持っている彼・彼女らが、校長と外部からの指導者採用を決めている。また、各運動部が適切に運営されているかもモニターし、学校運動部の理念に反する不適切な指導があった場合には、教員であれ、外部からの指導者であれ、運動部指導から外す権限も持つ。つまり運動部指導の人事を担っているといえる。
日本に求められる「公平に報いるシステムと運営管理」
日本では教員の部活動の負担を軽減するために、外部からの指導者を迎えること、民間業者に委託すること、地域に移行するという3つの策で対応を試みている。教員以外の人物が指導を担うことは時代の要請であるだろうし、指導者資格についても整備が進められているように見受ける。指導を受ける生徒にとっても、学校運動部という1つの集団に縛られることが減り、教員以外の信頼できる大人と接することで視野が広がるという効果もあるのではないか。
しかし、これら複数の策を実行するとなると、これまでよりも運動部の運営やマネジメントが複雑になるだろう。前述したように、米国では、アスレチックディレクターが外部へ応募をかけて適任者を採用しているが、この作業だけでも簡単ではない。
日本では、これに加えて民間委託や地域への移行、地域との連携も進める方針だ。平日だけ運動部指導に関わりたい教員、週休日も運動部指導を希望する教員の配置、地域移行や連携のために必要な規則作りなど、部活動改革に伴いマネジメント業務は増える。けれども、日本には、米国のアスレチックディレクターのようなポジションはない。これまで無理を強いられて運動部指導をしていた教員の負担は減るだろうが、新たに増えるマネジメント業務を無償で引き受けなければいけない学校の管理職や地域活動の代表者が出てくるのではないだろうか。

スポーツライター
スポーツ紙で日本のプロ野球を担当。1998年から米国に拠点を移しメジャーリーグを担当。2001年からフリーランスのスポーツライターに。現地に住んでいるからこそ見えてくる米国のプロスポーツ、学生スポーツ、子どものスポーツ事情を伝えている。著書『なぜ、子どものスポーツを見ていると力が入るのか』(生活書院)、『帝国化するメジャーリーグ』(明石書店)、共著『運動部活動の理論と実践』(大修館書店)など。Twitterは@zankatei
(写真:本人提供)