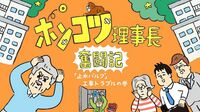倍率13倍、新設3年「農大稲花小」が超人気な訳 つねに高倍率、都会のど真ん中の意外な学び
ほほ笑ましいエピソードだが、これはアレルギーを持つ児童にとってのクルミという「危険」を、知識で回避しようとした「冒険」の一例といえるだろう。友達のことを知り、守ろうとするコミュニケーション能力が育っている証しでもある。夏秋氏は「高学年になればさらに自分を知り、より高度な挑戦に向かっていくことができるようになるでしょう」と続ける。
新設校だからできる大胆な働き方改革とオンライン化
「わが子を危険にさらしたくないという保護者の方もいます。しかし、変化を続ける現代社会で、子どもは親世代も経験したことのない未来を生きていきます。そのためには語学力やコミュニケーション能力はもちろん、冒険心が必要不可欠なのです」
こうした教育を徹底するため、同校は保護者にも一定の理解を求めている。座学と体験でサイクルをつくるように、学校と家庭、それぞれの指導でもサイクルをつくるのが同校の方針だ。入試の際には保護者の職業観などについても確認するという。
「本校はまだ新しい学校で試行錯誤なところもありますが、応援してくれる保護者が多く、とても助かっています。子どもにとっても保護者にとっても、教員にとっても楽しい場所。それがわれわれの理想とする小学校です」

新設校だからできる大胆な改革も、保護者の理解を得て実現させている。前述のアフタースクールもその1つだ。この取り組みで、同校は子どもだけでなく、教員の放課後をも有意義なものにした。
「子どもたちを全面的にアフタースクールに任せて、教員の時間外勤務を極力をなくしました。本校には熱心な教員が多いのでつい仕事をしてしまいがちなのですが、力の入れどころを定めることで、つねにいいパフォーマンスを発揮できるようにしています。余裕のない働き方では教育の質も上がりませんから」
コロナ禍をきっかけに校内のオンライン化も進めたが、その成果は保護者や教員にとっても大きなものだった。
「昨年度は入試の面接もオンラインで行いましたが、子どもたちも伸び伸びした態度で臨んでいて、普段どおりに近い姿を見ることができ大変有効だと感じました。授業参観もオンラインで実施したところ、子どもたちの顔がよく見えるし、休み時間の様子などもわかると保護者にも好評です。形骸化していることは見直して、いいことはどんどん取り入れる。子どものために何がいちばんいいかをつねに探っています」
よりよい農大稲花小を、保護者も子どもも一緒につくっていってほしいと話す夏秋氏。新しさと不変性を併せ持つその教育方針で、今後も人気を呼びそうだ。
(文:鈴木絢子、撮影:尾形文繁)
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら