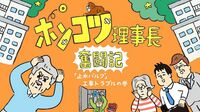倍率13倍、新設3年「農大稲花小」が超人気な訳 つねに高倍率、都会のど真ん中の意外な学び
そして最大の特徴ともいえる4つ目が、東京農大の小学校らしい体験型学習である。東京農大で副学長を務めた夏秋氏の人脈もあって、同大との連携も多く行われている。
「熱帯植物を専門とする教授に講義をしてもらい、マンゴーやサトウキビを試食したこともあります。稲作体験も実施しますが、ただ育てるだけでなく、稲を研究する教授を招いて世界の稲作について学んだことも。また、先日は2年生が神奈川県にある東京農大の農場に行きました。果樹園では柿やリンゴ、キウイなどを育てていますが、それらの葉を子どもたちに渡して、それぞれどの木のものかを探させたのです。見つけたら果実を採って味見できるというご褒美もあり、子どもたちは楽しそうに取り組んでいました」

体験型学習は、基本的な学びを定着させるための手段
東京の中心にありながら、子どもたちは日常的に豊かな自然に触れることができるのも、農大稲花小の人気が高い理由の1つだ。保護者の意向だけでなく、同校で学ぶ子どもたちは自然への関心が高いという。
「虫や動物が好きだという子どもが多いですね。将来の夢を聞くと、獣医師や漁師、農家になりたいという子もいます」
ほかではなかなかまねのできない取り組みが耳目を集める一方、夏秋氏は「本校は王道を行く小学校です」と断言する。

「重視しているのは、基本的な学びがきちんと定着することです。今、子どもたちはいろいろなことを本当によく知っていて、聞かれたことにもすぐに『知ってる!』と答えることができます。でもそれはインターネットや本で得た情報で、本人の経験ではないことが多い。本校の体験型学習では、そうした知識や座学の授業での学びを、実際に手に触れたり味わったりすることを通して、より深く身に付けるというサイクルができるのです」
育てたいのは、東京農大創設者の榎本武揚の言葉を基にした「冒険心」を持つ子どもだという。
「生きていくうえで、子どもたちは習ったことのない問題に必ず直面します。そうしたときに対処できるよう、学んだことを深く定着させ、さらに自分の中の知識をつなげるネットワークをつくってほしいのです。本校が目指す冒険とはいたずらに危険に飛び込むことではなく、対象を知り自分を知り、きちんと準備して未知のことにもチャレンジすることです」
例えば動物や植物に触れる機会の多い同校では、給食の時間なども使って、子どもたちのアレルギーへの理解を深めているそうだ。
「クルミアレルギーの子どもがいるクラスで農場へ行ったとき、子どもたちはクルミの木を見つけるとすぐに『○○ちゃん、クルミの木があるよ! 気をつけて!』と友達に教えていました」