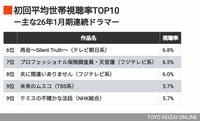学校から引っ張りだこ、芸人「オシエルズ」の正体 「笑いを取りたい」の前に大切なのが環境づくり
温かい舞台をつくるのは、表現者ではなく観客
――実際、ワークショップではどんなことをするのでしょうか。
矢島 お笑いのネタは、いかに上手に表現するかが、一般的に重要だと考えられています。しかし表現が苦手な子が小学校の学芸会で下手な演技をしても、観客である保護者が冷たい反応をするわけではないですよね? つまり温かい舞台をつくるために重要なのは、受ける側、見る側のリアクションなのです。
そのためワークショップでは、インプロを見て感じたことを共有したり、最高のお客さんでいるためには、どうしたらいいかを考えたりして、見る側の観点の大切さを知ってもらいます。そうすることで自分の考え方を変えることや、相手の考え方を受け入れることができるようになるのです。
発表の場で、いちばん面白い人だけが評価されるのは、それを得意とする人だけが楽しい授業です。でも聞く側である観客の姿勢がちゃんとしていれば、表現やコミュニケーションが苦手な人にとってもいい授業になる。それがわかると子どもたちも、安心できるんです。
――それらを伝える際に、お笑い芸人だからこそ、生かされている視点や技術はあるのでしょうか?
矢島 僕は大学で“面白いとは何か”という笑いのスキルについて、研究をしていました。そこで見つけた笑いの能力の概念4つをベースに、ワークショップなどを行っています。
1. 表現力
表現者はもちろん、観客も表現力を持ってリアクションを取ることが大切です。
2. 創造的思考力
例えばカップに半分残った水を、「もう半分しか残っていない」と捉えるか、「まだ半分残ってる」と捉えるかなど、見方は変えることができます。マイナスの出来事をプラスに捉えられるように、逆にプラスの出来事の裏にはマイナスが起きていることにも気づけます。
3. コーピング力
コーピングとは「対処する、取り除く」という意味で、緊張や不安を自分でコントロールする力です。例えば、授業で教師は準備に頼りすぎたり、過去の経験にとらわれすぎるのではなく、今に集中して子どもたちに求められていることに応える必要があります。コーピング力を高めることで、これらがやりやすくなります。
4. 論理構成力
ふり、ボケ、つっこみのように、話を整理し、筋道を立てて考えたり、説明する力です。
学校の先生はもちろん、子どもに教える際も、この笑いの概念をベースに伝えています。

野村 先生たちから「笑いを取れる授業をしたい」と、相談を受けることがあります。皆さん、芸人のように笑いを取りたいと思っているようですが、本当に大切なのは表現だけを追い求めるのではなく、お互いに笑い合える環境であるかどうかだと思うんです。これができていればつまらない話でも子どもたちは笑うし、逆にできていないとどんなに面白いことを言っても、笑えないと思います。
矢島 僕らも舞台ではネタを突然行うわけではなく、最初にお客さんをいじって、場を温めるために関係性をつくります。学校生活も同じで、先生と児童・生徒がいい関係をつくってからでないと意味がないんです。怖がられている先生がいきなり面白いギャグをやっても、子どもたちはなかなか笑えませんよね(笑)。こういう環境づくりがうまくできていない高校や大学は、退学率も高いように感じます。いい環境をつくるために、先ほどの1〜4の概念を理解することが大切です。
――ほかにいい環境をつくるために、大切なことはありますか?
矢島 自分の優位特性を知ることも重要です。もちろん観客側の表現も大切ですが、表現する側も自分の得意な方法を知るべき。しゃべりで笑いを取るのは苦手でも、絵や音楽、文章でなら面白さを伝えられる人もいます。先生の中にも、話は苦手でも黒板アートや学級通信が得意な先生はいるかもしれません。そういういろいろな笑いの可能性があることは、先生や児童・生徒にも伝えています。