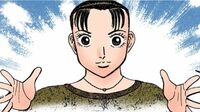ITやプログラミングから女子中高生が遠のく訳 女性の活躍を阻む「無意識バイアス」の壁
「小学生の時点では、男女問わずみんながプログラミングを楽しんでいるのに、中学生以上になると、突然プログラミング関連のイベントに参加したりIT職を目指す女の子が減ってしまう現状を目の当たりにしたのです。ここをテコ入れしなければと思い、Waffleを立ち上げました」と田中氏は話す。
中高生は、性別や職種に対する意識の感度が高まる時期なのだろう。そのタイミングで、ITやプログラミングから女子生徒が遠のいていく背景には、理数系科目やITを教える教員は圧倒的に男性が多いという事情も潜んでいるという。
その職に就く身近な人の性別が、その職を目指す子どもに影響を及ぼすという研究結果もある。数学または理科の先生が男性であった場合、「理系は男の子の進路」といった無意識バイアスが生まれる可能性が高く、理系を志望する女の子が減ってしまう。このような、現状の男女比がもたらすロールモデル効果による無意識バイアスの影響は大きいようだ。
女性不在のIT業界を放置してはならない理由
自身もデータサイエンティストとして働いていた斎藤氏は、「AIのアルゴリズムや学習データに男女の偏りがあると、AIでも性差別をしてしまいます。米国においてAIの学習過程で男性のデータを多くインプットしたことによって女子学生のエントリーがはねられてしまい、開発中止となった採用AIの事例は有名ですが、男性中心の業界で生み出されるサービスには、意図せずとも性差別が発生してしまう可能性が高まります。作り手の中に女性がいないと、そうした不具合に気づくことも困難になります」と説明する。

アリゾナ大学で計量経済学の修士号を取得後、外資系IT企業やAIスタートアップにてデータサイエンティストとして従事。2020年よりIT分野のジェンダーギャップへの問題意識からWaffleへ参画、共同代表として主に事業開発を担当。20年Forbes JAPAN誌「世界を変える30歳未満30人」受賞
(撮影:尾形文繁)
これからは、AIやロボットなどが、あらゆる産業や社会基盤に取り入れられていくSociety 5.0の時代だ。IT業界のジェンダーギャップが、企業サービスや社会基盤の不具合を生む可能性を高めるのだとしたら、本当に深刻な問題である。
田中氏は、「OECDが実施している国際的な学習到達度調査(PISA)の結果を見てもわかるとおり、日本の女子生徒の理系科目(数学的リテラシー、科学的リテラシー)の能力は非常に高いです。能力があるのに、世界的にも成長産業であるIT業界に就く人が少ないのは、極めて重大な機会損失だと感じています」と話す。
また、斎藤氏によれば、IT職に就くために必要な能力に男女差はないそうだ。さらに、IT職は非肉体労働で勤務場所の制約も少ないので、本来は、出産などのライフイベントの変化による影響を受けやすい女性に向いている仕事だという。
女性のIT人材が依然として少ないのは、現在の男女比によって生じてしまう無意識バイアスを、多くの人が払拭できていないからなのかもしれない。それゆえWaffleは、将来に向けた進路選択や文理選択を行うタイミングである「中高生」というポイントにターゲットを絞って、教育活動や政策提言を行っている。中高生時代が女性にとって、その後の意識に大きく影響を与える時期だと考えるからだ。
かつて、理系出身の女性に対して、「リケジョ」というネーミングが生まれたが、Waffleは、あえて「ITガールズ」や「テック女子」といった呼称をしない。その理由は、「女の子だから」「男の子だから」という意識によって、選択する職種や自分の可能性を制限してほしくないからだという。