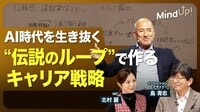日本の文化財・観光政策をはじめ、日本経済の課題解決に関して積極的な提言を行っているデービッド・アトキンソン氏。米金融大手ゴールドマン・サックスでアナリストをしていた時代には、バブル崩壊後の銀行が抱える巨額不良債権をいち早く指摘。業界の批判をよそに、間もなく主張の正しさが明らかとなり「伝説のアナリスト」として一躍有名になった。
その後、国宝や重要文化財などの補修を手がける小西美術工藝社社長に就任。『新・観光立国論』(東洋経済新報社)をはじめ、『日本人の勝算』『日本企業の勝算』(同)など次々と日本経済に関する提言を行い、注目を集めている。現在は、政府の成長戦略会議のメンバーとしての活動も行うアトキンソン氏は、日本の教育改革をどのように見ているのか。
小中高より大学改革のほうが優先順位が高い
――人口減少、少子高齢化が進む中、現在の日本経済の力を将来的に維持できるのか、今盛んに議論が行われています。その中でも教育改革は将来の日本の行方を左右する重要な問題ですが、現在の教育改革の方向性についてどんな評価をされていますか。
将来の日本経済を見据えて、今現在において何をすべきか。その改革のポイントになるのは、まず大学だと私は考えています。通常、こうした教育問題については、小中高がクローズアップされがちですが、彼らが社会の中核人材となるのは30~40年後。確かに基礎教育を行う小中高の改革は重要ですが、国力や生産性の観点からいえば、大学改革のほうが優先順位が高いといえるでしょう。とくに、日本における最大の課題である生産性向上に関しては、小中高の教育よりは、大学教育の良しあしが最も関係しているという分析の結果に注目したいです。

今、問題となるのは「大学で何を教えるべきか」ということです。世界経済フォーラムの分析によると、日本の大卒のスキルランキングは42位と極めて低い評価です。とくに欧米と比べ、日本の大学では「クリティカルシンキング(批判的思考)」教育の重要性に対する意識がないようにみえます。同じく世界経済フォーラムの19年のデータでは、日本の「クリティカルシンキング教育」は141カ国中87位でした。衝撃的な事実だと思います。私は今こそ、日本の大学はクリティカルシンキングを強化するべきだと考えています。
ある研究によれば、物事を論理的に考えるクリティカルシンキングができる適齢期は、子どもの脳の発達成長過程からすれば、18歳以降だといわれています。つまり、脳の発達から考えても、小中高よりも、大学入学時の年齢がクリティカルシンキングを教えるタイミングと合っているということなのです。
――中学生や高校生にクリティカルシンキングを教えるのは早いということですか。
多少の要素は組み入れることができますが、実際には極めて難しいといえます。日本の小中高では詰め込み教育がよく批判されますが、クリティカルシンキングを教えるという意味では、小中高までは基本的に詰め込み教育をする場で、大学はクリティカルシンキングを訓練する場所だと考えています。