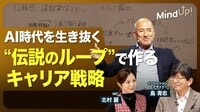それは、高校までの仕組みが違うからだと思います。イギリスでは16歳で、一般的な幅広い教育から大学で勉強したい項目に絞って勉強します。大学で受ける教育の準備を始めるわけですが、アメリカでは、それを大学1年生の時に行うと聞いています。
大学の制度は欧州から始まっていますが、優秀な大学ほどクリティカルシンキングを学ぶことを徹底させています。大学の成り立ちを歴史的に見ても、大学の使命はクリティカルシンキングを学ぶことにあるのです。
――なるほど。ならば日本の大学はどうすべきなのでしょうか。
英語圏の論文はほぼネットで読むことができます。ネットの普及によって、大学に通わなくても、その膨大な知識にアクセスすることができます。その中に、IQの高低と社会的に成功するかどうかや幸せ度の相関関係は低いという研究成果があります。つまり、IQの高い人が必ずしも社会的に成功するとは限らないのです。
それよりは、クリティカルシンキングができる人のほうが、出世する確率が高く、人生の場面場面で的確な判断をすることができる力を身に付けていることから、幸せな人生を送る確率が高くなって、その相関関係が強いと分析されています。
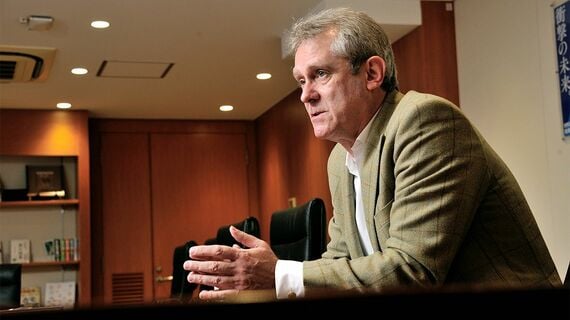
一方、日本の大学はどちらかといえば、IQを重視する傾向があります。しかし、ここで興味深いことは、クリティカルシンキングができる人はI Qが高い傾向にありますが、ただIQが高いからといって、クリティカルシンキングの能力が高いとは限らないのです。必ずしも同じではないということ。つまり、IQが最も高くなくても、クリティカルシンキングもピアノと同じように訓練すれば、身に付けることができるのです。
オックスフォード大学は、成績だけで入学できる学校ではありません。私は高校時代、5位の成績だったのですが、1~4位の成績の人は皆不合格でした。合格基準は、その人がクリティカルシンキングをできる見込みがあるかどうか。そこを重視しているのです。それさえ教授陣が認めれば、共通試験を受けたかどうかに関係なく、入学することもできるのです。
つまり、IQ的な頭の良しあしではなく、その人が自分の能力をきちんと使えるかどうかが重要であり、その使い方を教えることが大学の役割なのです。その意味で、日本の大学もクリティカルシンキングの訓練学校であるべきなのです。
――クリティカルシンキングは、日本経済にどんな効果を生むのでしょうか。
今から大学改革をしてクリティカルシンキングを教えれば、4年後にはその人たちが社会に出てきます。人口減少で日本経済が伸び悩む中で、いちばん早く効果が出る施策になるはずです。しかも日本の大企業経営者や官僚のほとんどは大卒です。これから社会を動かしていく資格のある大卒者が、クリティカルシンキングができないというのは、決定的な問題なのです。国としての設計ミスだともいえるでしょう。
クリティカルシンキングは、判断しなければならないときに、正しい判断をするために使うものです。知識が豊富でも判断が間違っていれば、成功や成果には結び付きません。どんなに難しい局面であれ、いかに正しく確率が高い判断をすることができるのか。国の経済政策であれ、社会政策であれ、どのように改革すればいいのか。クリティカルシンキングさえできれば、よい方向に向かう確率を高くすることができるはずです。日本経済がバブル崩壊後、30年間低迷したままで、いまだに人口減少の対策を打てていない理由も、究極的にはクリティカルシンキングができていないことにあるのです。