東京学芸大学附属竹早小学校の佐藤正範先生に聞いたBYOD事例 「先生のマインドチェンジを促すオンライン授業」

「黒板」によって生じる先生のマウンティング
――初めてのオンライン授業に対し、先生たちの反応はいかがでしたか。
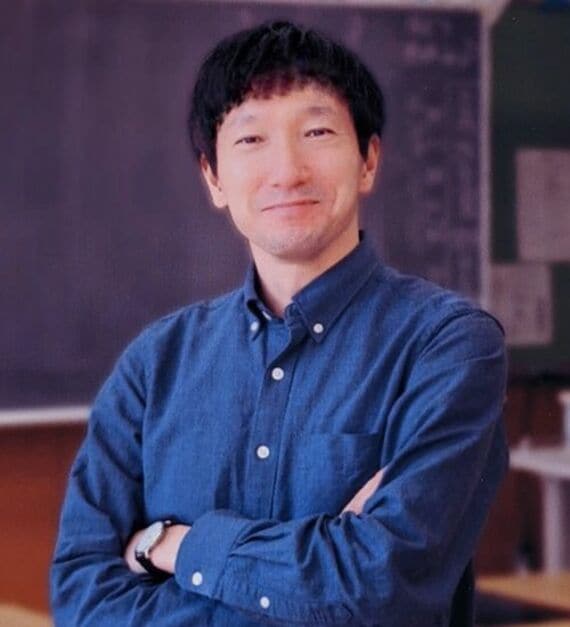
多くの先生が、画面越しに子どもたち1人ひとりの顔が見られる状況を目の当たりにして、「オンラインだと、子どもたちの興味や注意を引きつけるのがこんなにも難しいのか」と驚いていました。
現在本校が参加している「未来の学校みんなで創ろう。プロジェクト」にて、コロナ以前から学校内外の関係者とオンライン会議をする機会があり、プロジェクトメンバーや管理職など職員の3割程度はツール自体に抵抗はなかったと思います。しかし、子どもたちに向けたオンライン授業の施行では、参観した多くの先生方にもさまざまな気づきがあったと感じます。
――具体的には、どのような気づきがあったのですか。
現在の日本の学校は、先生1人に生徒30〜40人という集団授業が前提なので、授業の展開を教師がコントロールするスタイルが主流です。そして、ほとんどの授業で使用される「黒板」は、実は教師にとって手放しがたい強力なツールなのです。
教室という特殊な空間の中に、1人の大人とたくさんの子どもたちがいます。その1人の大人が黒板に板書すれば容易に子どもたちの注意を獲得することができますから、集団授業において「黒板」はなくてはならないツールです。しかし、このような授業スタイルや、子どもたちを「揃える」ことを良しとしてきた旧来の「教授」スタイルでは、意図せずとも教師がマウンティングを取ってしまうことにつながります。
オンライン授業では、教室の空間的な特性はなくなります。また、物理的に対面しないことにより大人と子どもという上下関係も希薄になるのか、子どもたちが教師の話に飽きている様子もあからさまに見えてしまうことがありました。初めてオンライン授業を施行したときに、そんな子どもの様子に驚いた先生は多いと思います。
子どもは大人の顔色をうかがって、こちらが望んでいる反応を返してくるものなので、もしかしたら、オンライン授業で退屈そうにする子どもが本当の姿なのかもしれないですね。オンラインでは、子どもの興味を引きつけることがすごく難しいと感じるとともに、これまでは教師がいつもマウンティングを取ってしまっていたのだろうなと気づきました。
































