ならば、軍部の台頭をもたらした原因は何か。結論を急げば、その原因こそ、健全財政にほかならなかった。
恐慌による中間層没落とファシズム
1929年に成立した浜口雄幸内閣は、井上準之助を蔵相に任命し、金解禁(金本位制への復帰)を成し遂げるため、緊縮財政を断行した。そして、世界恐慌が始まっていたにもかかわらず、1930年1月、金解禁を実行した。
その結果、日本経済は恐慌となり、倒産や失業が増大し、とくに農民と中小企業者は深刻な打撃を受けた。それにもかかわらず、井上は金本位制という財政規律を維持し、かたくなに健全財政路線を守り続けた。
こうして困窮し、没落した中間層は過激な労働運動や右翼的な運動へと走った。こうして軍部が台頭し、わが国は軍国主義化していったのである。
このように、恐慌(デフレ不況)によって中間層が没落し、ファシズムが生まれるという現象は、同時代のドイツなどでも見られた現象である。
実は、高橋はデフレが失業を増やし社会問題を引き起こすことを、1918年の段階ですでに理解していた。
増加すべき当然の理由ありて増加したる通貨を急激に収縮したりとせんがために物価は下落すべしといへども、物価の下落は一面において不景気となり、失業者の増出を予想せざるべからず。したがつて重大なる社会問題の発生を見るべし。(経済論)
また、社会問題が発生すれば、人心が乱れ、過激な思想が台頭することも高橋はわかっていた。次の引用は、関東大震災の翌年の彼の言葉である。
この秋に於て私などの深く考へて決心したるところは、このままただ移つて行けば、政治問題が軈ては社会的問題になり、社会的問題になつて、全国にこの不平が起れば、燎原の火のごとく人心は激昂して来る、いづれのところに止まるか分らない。それゆゑにこれを要約して申しますれば、吾々の考へはかくのごとく極端に国民の思想を激発しないやうに、政治問題の範囲に於てこれを喰止めたい。(随想録)
しかし、井上準之助による健全財政が招き寄せた軍国主義は、もはや高橋の手に負えるものではなかった。その軍国主義の凶弾によって、高橋は倒れたのである。
国民の失業や困窮を放置すれば、人心が乱れ、思想が過激化し、ファシズムを生み出しかねない。これこそが、本当の「歴史の教訓」である。
現在、世界恐慌以来、最悪と言われるコロナ危機にあって、倒産、失業、貧困が急増し、国民の生活に対する不安が高まっている。それにもかかわらず、政府は、財政健全化の呪縛にいまだにとらわれ、十分かつ迅速な経済対策を打ち出せていない。
これが何をもたらすのか。為政者は「歴史の教訓」に学ぶべきであろう。
著者フォローすると、中野 剛志さんの最新記事をメールでお知らせします。
著者フォロー
フォローした著者の最新記事が公開されると、メールでお知らせします。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。
なかの たけし / Takeshi Nakano
1971年生まれ。東京大学教養学部卒業後、通商産業省(現・経済産業省)に入省。2003年にNations and Nationalism Prize受賞。2005年エディンバラ大学大学院より博士号取得(政治理論)。主な著書に『日本思想史新論』(ちくま新書、山本七平賞奨励賞)、『富国と強兵』(東洋経済新報社)、『TPP亡国論』(集英社新書)、『政策の哲学』(集英社)など。主な論文に‘Hegel’s Theory of Economic Nationalism: Political Economy in the Philosophy of Right’ (European Journal of the History of Economic Thought), ‘Theorising Economic Nationalism’ ‘Alfred Marshall’s Economic Nationalism‘ (ともにNations and Nationalism), ‘ “Let Your Science be Human”: Hume’s Economic Methodology’ (Cambridge Journal of Economics), ‘A Critique of Held’s Cosmopolitan Democracy’ (Contemporary Political Theory), ‘War and Strange Non-Death of Neoliberalism: The Military Foundations of Modern Economic Ideologies’ (International Relations)など。

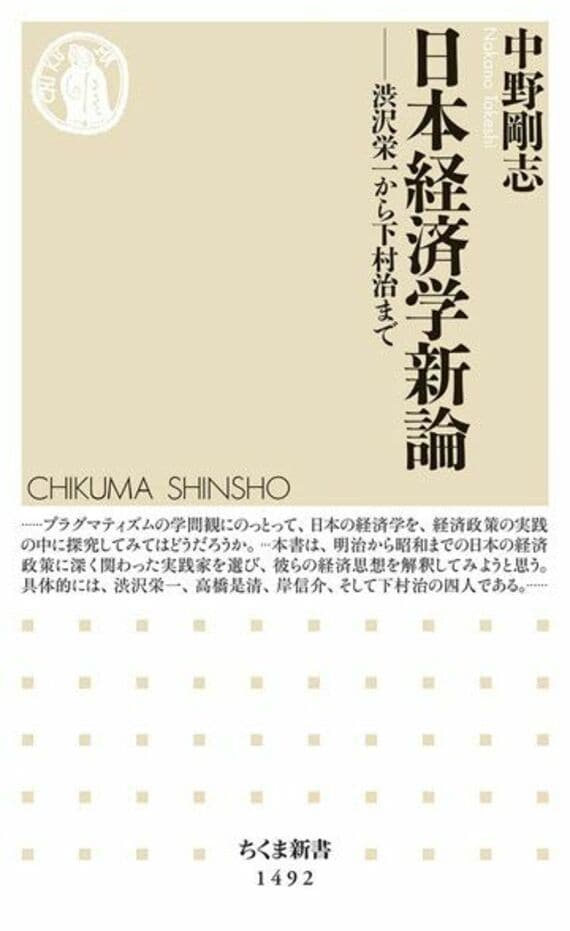






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら