「魔の6月」にも有効、荒れた学級も3日で雰囲気が変わる"教師の声かけ"の工夫 安定した学級経営に重要な「認める」声かけとは
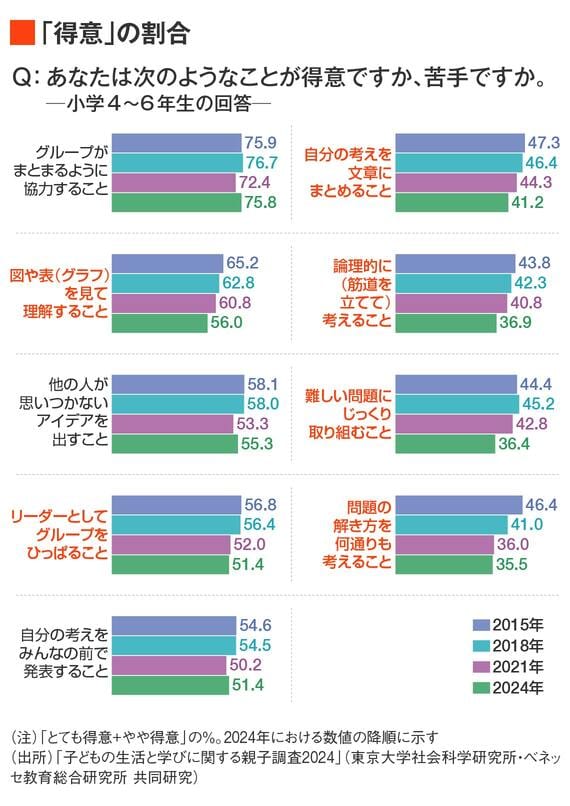
「教師はどうしても目立つ子どもに意識がいきますので、問題を起こさないような子どもをいかに丁寧に見ていくかが重要。目立たなくてもやるべきことをやっている子に対しては、『今日は頑張って発言したね』『班の代表としてしっかり発表ができてすばらしいね』と、その子にとってはチャレンジだったことを認める声かけをすることが大切です。1人ひとりの小さな変化に気づくには、教卓から離れて教室内を歩き回る時間を増やしてほしいと思います」
問題行動を起こす子どもに対しては、「本人や周囲の子どもたちの安全が確保されていれば何もせずに様子を見る」のが庄子氏の基本的なスタンスだ。
「負の注目を集めると問題行動がエスカレートすることがあるため、問題行動には過剰に反応せずに、『今日はちゃんと座っていられるね』とよい行動を認める声かけを繰り返すことが重要です。問題行動の背景に複雑な事情が隠れているケースもあるため、対応に悩む場合は担任だけで抱え込まずに、学年主任と共有したうえで管理職やスクールカウンセラーに相談してみるとよいでしょう」
学校に行き渋る子どもに対しては、庄子氏は「背景にあるものはさまざまなので一概には言えない」と前置きしたうえで、「『明日は学校に来れるかな』とプレッシャーをかけるような声かけは避けたほうがよい」と話す。
「学級内に苦手な子がいる可能性もあるため、『みんな待っているよ』とは言わないほうがよいですし、行き渋る子は既に頑張っているので『頑張って学校に来よう』という声かけも避けるべきです。『登校できても、できなくても、私はあなたと話せてうれしいよ』と伝え続け、教員自身がその子との会話から学べることを学ぼうという姿勢を持つことが大切です」
子ども同士のトラブルが起きた際は、どのような声かけを意識するとよいだろう。庄子氏は「すぐに仲よくなれなくてもいいからね」と伝えてから、「これからずっとこのことでけんかするのは嫌だよね。どうしたい?」と双方の意見を聞いて対応策を一緒に考えるよう心がけてきたという。
「教員はトラブルの解決を急ぐあまり、子ども同士が納得していないのにとりあえず謝らせて話し合いを終わらせようとすることがあります。しかし、人間関係のトラブルはすぐに解決しないことも多いので、裁判官のような立場で正すのではなく、一緒に考える姿勢で向き合うことが重要です」
夏休みまでのカウントダウンで「魔の6月」を乗り切る
6月は多くの学校において大きな行事がないこともあり、子どもたちが中だるみして学級が不安定になりやすい「魔の月」とも言われている。この時期にはどのような声かけを心がけるとよいのだろうか。
「『あと30日、登校したら夏休みだね』というように、終業式から逆算した日数を意識させる声かけをすると、子どもたちは終わりが見えて頑張れるものです。授業の単元の終わりに発表会を開いたり、総合的な学習の時間などを活用してイベントを企画したりして、単調な毎日に変化をつけるのもよいでしょう」
6月の時点で学級が不安定になっている場合は、「教員がもう一度、4月のような新鮮な気持ちで子どもたちと接してみてほしい」と庄子氏はアドバイスする。
「『今週は自分ばかりが喋りすぎないようにしよう』『今日は普段はあまり注目していない子に目を向けてみよう』というように、1週間単位、1日単位で目標を立てて過ごしてみると、子どもたちとの関係も変わっていきます。笑顔で接することができるように、まずは教員自身がしっかり休んで自分の心の状態を整えることも意識してみてください」
(文:安永美穂、写真:つむぎ/PIXTA)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
































