「独学で東大合格」、座談会で明かされる"塾なし東大生"の共通点4つ、板書にノートは使わない? 板書の仕方、学習習慣、保護者や教員との関係性
Bさん「私も、板書を写すことはしていませんでした。黒板に書かれている内容はほとんど教科書や参考書に載っているものなので、わざわざ書き写す意味を感じませんでした。逆に、教科書に載っていない情報や先生の小話などをその場で教科書やプリントに直接書き込むことで、自分だけのノートを作っていました。教科書やプリントを読めば、当時の授業の雰囲気まで思い出すことができるようになりました」
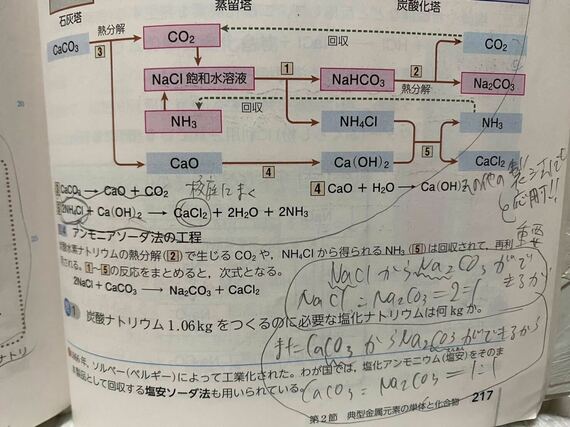
Cさん「私もノートは取っていませんが、2人とは全然違う理由です。私の学校は非進学校なので、授業の進度がとても遅かった。このペースでやっていたら東大には間に合わないので、授業中は先取り学習や別の教科を進める“内職”をしていました。なのであまり授業内容は覚えていないのですが、その分自分の勉強をどんどん先に進められました」
高校に通っていない私はもちろんですが、座談会のすべての参加者が板書を写していないという結果でした。後日、他の独学東大生十数名に行ったアンケートでも、板書をそのまま写していた人はほとんどいませんでした。
保護者や指導者はついノートを取っているか否かに注目してしまいますが、板書をただ写すだけではなく、授業内容をしっかり想起できるような仕組みが作られているかに目を向けていくことが、成績向上の第一歩だと思います。
「毎日やりきる“仕組み”を作る」学習の習慣化の共通点
塾なしのもう一つの難しさは、学習習慣を作ることにあります。自由に学習計画を組めるからこそ、つい怠けてしまいがち……。
さまざまな学校行事と両立しながら、彼らはどのようにして学習習慣を作っていったのでしょうか。
Bさん「部活が忙しい分、自律して学習をする必要がありました。ここで役に立ったのが、片道1時間の通学時間です。高校に通いたての頃は長い通学時間が苦痛だったのですが、逆にこの時間が勉強習慣につながりました。電車内は勉強をする場所、と決めていたので、最低でも1日2時間は勉強できました。放課後は学校の空き教室に残って勉強していたので、毎日3-4時間程度は勉強していました。通学時間や学校に存在している時間が“強制的な学習時間”になっていたのは大きかったと思います」
Cさん「1日たりとも勉強しない日を作らない、というのが自分のこだわりでした。たとえ体調が悪くても、どんなに忙しくても、5分は必ず机に向かう。そうすると学習習慣は途切れないのです。東大入試を決めたときから、入試の合格発表日まで1日も休まず勉強を続けていました」

1998年生まれ。中学生のときに東大を目指すことを決め、高校にも塾にも通わず、通信制のNHK学園を経て、独学で2018年東京大学文科Ⅰ類合格。東京大学法学部を卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、“独学3カ月コーチング”の「オーバーフォーカス」や“東大生が作る国語に特化した個別指導”の「ヨミサマ。」を立ち上げる。著書に自分自身の独学ノウハウを詰め込んだ『成績アップは「国語」で決まる!』がある(X:@Kanda_Overfocus)
(写真は本人提供)
ここで、私がおすすめする学習習慣の作り方は、私自身も中学生のころ取り組んでいた、「1日30分より長く勉強をしない」というユニークな方法です。1日の勉強時間は、30分以内であれば何分でも構いません。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら