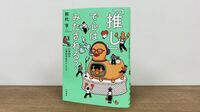「小学生の推し活」、親はどう向き合う?子どもの心にもたらされるメリット3つ 理解できなくても「好き」を発見した喜びを共有

コロナ禍や一人一台端末を背景に小学生に広がる「推し活」

愛知淑徳大学 心理学部 教授
1974年東京都生まれ。日本女子大学大学院人間社会研究科心理学専攻 博士課程修了。博士(心理学)。日本学術振興会特別研究員、京都大学 霊長類研究所研究員、京都大学こころの未来研究センター助教などを経て、現在、愛知淑徳大学心理学部教授。専門は実験心理学、生涯発達心理学、認知科学。著書に『女性研究者とワークライフバランス』(新曜社、2014年)、『「推し」の科学 プロジェクション・サイエンスとは何か』(集英社新書、2022年)など。高校生(かなり推し活あり)と小学生(やや推し活あり)の二児の母でもある
(写真は本人提供)
「推し活」といえば、アイドルのファンやアニメファンの間で行われてきた「オタク」的な活動に端を発するイメージがあるが、今では学校生活や仕事の傍ら、推し活にいそしむ人が少なくない。
推し活について心理学の立場から研究してきた久保氏によれば、推し活は「プロジェクション」という認知科学の概念からも説明できるという。
「私たちは、外部から得た視覚や聴覚などによるさまざまな情報を受容し、自分のなかで“表象”をつくります。そこには自分だけの意味や価値があり、それらを再び外の世界へと投影し、心と外界をつなげる。それが“プロジェクション”という働きです」
例えば、友人が赤いスマホケースを持っていたとする。私たちにとっては単なる「赤いケース」だが、もし友人が「赤がメンバーカラーのアイドル」を推しているとしたら、それは「推しのカラーのケース」という大きな意味をもつ。推しに関連する色や数字に思い入れを抱いて自分でも身につけることなどは、推し活でよく見られる自己表現の1つだ。