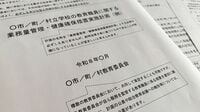「精神疾患で休職が過去最多」への対策急務、教員に燃え尽きが生じやすい訳 悪循環から抜け出すメンタルヘルスケアとは
例えば、業務の見直しについて学年や校務分掌の垣根を越えた小グループでの話し合いを持てれば、コミュニケーションのしやすさが増し、お互いの日ごろの様子がわかるようになります。メンタルヘルスケアで大事なのは “いつもと違うな” という気づきです。働き方改革のミーティングを重ねて普段の様子を知っていれば、変化に気づきやすくなります。 “あれ、いつもとちょっと違うけれど、大丈夫?”といった声がけやねぎらいが生まれ、自然なラインケアがしやすくなるのではと思います。
健康管理を専門家に外注する教育委員会も
──10年前の検討会議の最終まとめでは、学校のメンタルヘルスケアを行うキーパーソンは校長等であるとして、教職員のストレス状況の把握や復職後のサポートなどラインケアの充実が提唱されました。しかし大石先生は、現状ではそれを見直し、専門家を活用する発想に切り替えるべきだとおっしゃっています。
当時は、校長先生に職場の衛生管理者として当事者性を持ってほしいとの思いがありました。ただ、10年経った今、管理職の多忙さを考えると、校長先生が復職支援にあたるのは難しいでしょう。民間企業などでは産業医や産業保健師が復職プログラムを作成し、管理職はその報告を受け、直接的には携わりません。精神疾患の原因がパワハラだったような場合は復職を遅らせる恐れもあるからです。
──職場で労働者の健康管理などを行い、専門的立場から指導・助言をする医師である産業医は、どの程度配置が進んでいるのでしょうか。
産業医の選任など学校の労働安全衛生管理体制の未整備も課題です。常時50人以上の教職員がいる学校には、産業医の配置、月1回の学校巡視などが義務付けられていますが、巡視実施率は小学校で54.5%、中学校で62.8%にとどまります(文科省「令和3年度公立学校等における労働安全衛生管理体制等に関する調査」)。教職員50人未満の学校には産業医の選任義務はないため配置されていない学校も多くあります。
現状に即した選択肢としては、健康管理サービスを提供する企業と提携したアウトソーシングが考えられます。産業医や産業保健師から健康管理のサービスを受けられ、不調を相談できる仕組みや、休職者が安定して復職できる支援が受けられるというものです。
──文科省が2023年度から開始した「メンタルヘルス対策に関する調査研究事業」では、教育委員会と企業が連携したモデル事業が展開されています。2024年度は新たに、このモデルの分析・助言や、横展開に向けた取り組みをするとしていますが。
教職員のメンタルヘルスは、子どものメンタルヘルスに直結する問題です。家庭で虐待やネグレクトに遭っている子どもたちにとって、表情が険しく時々涙ぐんでいるような先生には相談できないでしょう。子どもの自殺数は教職員のメンタルヘルス不調者とパラレルに増えています。相関があるというデータはありませんが、生きづらい子どもたちにとって学校の先生は力になってほしい。子どもの自殺対策の文脈からも教職員のメンタルヘルスは重要で対策の充実が急がれます。
(文:長尾康子、注記のない写真:kapinon / PIXTA)
関連記事
【後編】校長の負担が大きい、「精神疾患で休職の教員」対応に見る学校の課題
【前編】「抗不安薬を飲んで学校に」、精神疾患で休職の教員が増えている訳
教職員「精神疾患で休職」が過去最多の6539人、学校と企業の決定的な違い
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら