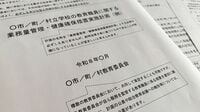「精神疾患で休職が過去最多」への対策急務、教員に燃え尽きが生じやすい訳 悪循環から抜け出すメンタルヘルスケアとは
──しかし、教職員のメンタルヘルス対策については、文科省の対策会議が2013年3月に「教職員のメンタルヘルス対策について(最終まとめ)」を取りまとめて以来、10年間見直しされていません。大石先生は当時、対策会議のメンバーでもありました。
働く人の心の健康問題や職場改善、復職支援といったことは保健医療福祉分野というイメージが強く、教育分野では自分事になりにくかったのではないでしょうか。自治体でも働き方改革と教員のメンタルヘルス対策を包括的に取り組んでいる自治体はまだ少ないでしょう。

北里大学 医学部精神科学 講師、北里大学病院相模原市認知症疾患医療センター長
1999年に北里大学医学部卒業後、北里大学東病院精神神経科にて研修。駒木野病院精神科、北里大学医学部精神科学助教を経て、2019年より現職。2012〜2013年に文科省「教職員のメンタルヘルス対策検討会議」委員を務める。著書に『教員のメンタルヘルス——先生のこころが壊れないためのヒント』(大修館書店)などがある
(写真:大石氏提供)
検討会議で最終提言が取りまとめられたのち、私が関わる自治体ではメンタル疾患が発生しやすいハイリスク期間の異動後1年を念頭に置き、異動予定者を対象に予防的な介入を行ったり、管理職向け研修の見直しなどに取り組んだ結果、休職者のうち精神疾患が占める割合を減らすことに成功しました。
ところが数年後、数字は逆戻りしてしまいました。保健師を中心にケア体制を整えたり、管理職向けのラインケアの手引きを作成したりと試行錯誤していますが、一向に効果がありませんでした。
働き方改革の議論が進み、教員の業務量が整理されれば多忙感が弱まり、複雑な業務であっても先生方が“報われる”気持ちが増えてくれば休職者は減るのではと期待しています。ただ、改革がなかなか進まないことによって生じる現場の負担を考えると楽観できません。
働き方改革と一体化したメンタルヘルス対策が必要
──学校現場で、実際にメンタルヘルス対策を進めていくにはどうしたらよいでしょうか。
メンタルヘルスの取り組みも、働き方改革と同じで教育委員会のトップダウンだけではうまくいきません。学校という職場をよくしようと職場の人たち自身が意識を持つ必要があります。
メンタルヘルスケアは「セルフケア」「ラインによるケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」の「4つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要とされます。セルフケアは先生方が当事者意識を持つことが必要ですし、ラインケアは管理職やベテラン層がメンタルヘルスに優しい職場づくりを進めていく必要があるのです。
メンタルヘルス対策の研修で基本的な知識や対応を知ることも大事ですが、働き方改革というコンテンツにメンタルヘルスの観点を取り入れながら進めることも可能ではないでしょうか。というのも、働き方改革をうまく進めている自治体は、学校単位でモチベーションを喚起しながら改革を進める土壌づくりに長けています。そうした仕組みを応用するイメージです。