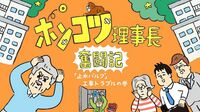成績だけで「やりたいこと」諦めないで、全国初「AI活用」した入試改革は 立命館×atama plus「入試改革」1年目の通信簿

2040年の大学進学者数は、約51万人になる——。文科省が「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)」で出したこの数字は、現在より約12万人も少ない数字だ。人口減少により大学志願者が定員を下回る「大学全入時代」が到来するとされ、すでに学生の募集を停止する学部、大学も出てくるなど「大学淘汰」の現実味も増してきている。
今後大学は、それぞれに合った適切な志願者を確保するためにも、各大学の教育目標・理念を明確に設定し、特徴や強みを打ち出すことがいっそう求められる。また少子化による大学経営の負担を取り除くという観点では、共同の研究機関や拠点を設けるなど、大学間ネットワークの構築も急務だ。
とくに、学生との最初の接点となる「入試」は、小学校・中学校・高等学校での学びとシームレスにつながり、子どもの学習のモチベーションを高められるようなよりよい形を、個々の大学にとどまらずに模索する必要がある。
そんな中、立命館大学は総合型選抜入試の出願条件にAI学習を課す「UNITE Program」をスタートさせた。具体的には、志望する学部で求められる数学の指定単元を、個別最適化されたAI教材「atama+」で学習した後、各単元の修得認定試験に合格し、プログラムを修了すると、出願資格が得られるという仕組みだ。
このプログラムの企画・実行を現場で担った、立命館大学入学センター事務部長の熊谷 秀之氏とatama plusのプロジェクト責任者である井上 拓也氏に取材。昨今の大学入試の課題から、学生の成長につながる入試のあり方、今後の入試に関する大学間連携などの展望を聞いた。
評定だけで足切りする入試への疑問
あの時もっと勉強しておけばよかった——。早くからやりたいことを決めていたら——。大人になってから、一度はそのように考えたことがある人も多いだろう。実際、大学の学部選びが将来の職業に与える影響は大きいが、「やりたいこと」よりも、目の前の「得意な教科を中心に」あるいは「苦手な教科を避ける」などして文系理系、またその先の進路を決める高校生は多い。

立命館大学 入学センター事務部長
熊谷:社会に出てやりたいことや大学で深めたいことを、高校1年生の4月から決められている子はかなり少ないと思うんですよね。例えば、それまでは部活動に一生懸命で勉強はおろそかになっていたけれど、高校2年生の冬に何かきっかけとなる経験をして「この分野でこういうことをやり遂げたい」と思う子もいるのではないかと。そうしたときに、評定が問われるこれまでの学校推薦型選抜や総合型選抜だと、成績の挽回が難しいから諦めなければいけません。
一般入試だけでなく、特別入試でもちゃんと挽回のチャンスがあるような、未来志向の入試の設計があってよいのではと以前から考えていました。これまでは特別入試では高校での科目の履修や学習成績の状況を参考にしていましたが、「履修した」という過去ではなくて「修得している」という現在の実績ベースで評価する、そんな入試を実現させたかった。それが今回のAI学習プログラムにつながっています。