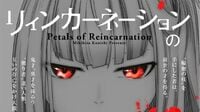【教員向け】教材を作る方法とは?小学校・中学校・高等学校における教材作成のコツを解説

教材作成に必要なこととは
大前提として、教材自体はあくまでも教育効果を高めるため、学習活動を達成するためのツールでしかありません。ですので、教材作りのスタートは学習指導要領等を踏まえ、各教科・領域の中で達成すべき目標を理解することからです。
教科学習などにおいては、授業する内容の教科書ガイド(指導書・参考書)を最初に確認するのがよいでしょう。そして、教科書ガイドと併せて学習指導要領の解説書なども見ることで、「基礎的・基本的な知識・技能」だけではなく、「思考力・判断力・表現力等」や「主体的に学習に取り組む態度」の学力の三要素についても、理解を深めて授業を実施することが可能になります。
教科書がない総合的な学習の時間やそのほかの「〇〇教育」といったものに関しては、文部科学省公式サイトや各自治体からのリーフレットで確認することをお勧めします。
こちらでは、教師向けの参考資料としての指導資料や学習評価についてまとめられています。
小学校の教材作成について
小学校の教材作成において、とくに留意すべきなのは「表現方法」です。
入学したての小学1年生と中学校目前の小学6年生では、言語スキル自体に大きな差があります。当然のことながら、これは学年だけではなく発達段階やバックグラウンドにも関係してくるものです。ですので、授業ユニバーサルデザインで意識されているような視覚化や構造化を図るなどして、誰もがわかりやすい・参加しやすいような学習環境をつくる必要があります。
学力の三要素(「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習 に取り組む態度」の3観点)についても、理解を深めて授業を実施することが可能になります。
中学校の教材作成について
中学校の教材作成において、とくに留意すべきなのは「指導と評価」の一体化です。
これに関しては小学校と同様ですが、教材となるワークシート自体が評価物そのものであったり、定期テストにおける重要なアイテムにもなったりすることがあります。ですので、教材作成の意図を明確に持ち、授業時における「何のため」の教材なのかを教員がよく理解していることが重要です。
指導・支援するためのツールとしての教材ですから、評価にも大きな影響力があるような教材が望ましいのではないでしょうか。
高等学校の教材作成について
高等学校の教材作成については、これまでの小学校や中学校と異なり、主体的に学びに向かえるような教材がいいでしょう。基本的な知識や勉強内容はネット検索すれば、出てくることが多く(いわゆるググれば出てくるという意味)、そのほか付随するような内容に関しても、検索結果として表示されるでしょう。
そうなると、これまでのような「暗記」のためのワークシートでは意味がなく、学習の学びを広げる・深める「きっかけ」となるような、優れた教材である必要があるでしょう。
そのためにはやはり、単元の目標に沿った教材選定・教材研究が重要となってきます。生徒の実情に合った(少しチャレンジするとポジティブな結果が出そうなもの)教材の取捨選択ができるのは、プロフェッショナルな先生だからこそです。