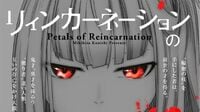【教員向け】教材を作る方法とは?小学校・中学校・高等学校における教材作成のコツを解説
主体的に学びに向かえるような教材という意味では、同時共同編集ができるようなクラウド型の教材も効果的です。GIGAスクール構想が進み、小中学校で経験してきている生徒たちが高等学校の生徒となっていますので、学習内容によって紙ベースのワークシートとデジタル教材としてのワークシートの併用は必須だと思われます。
効果的な学習教材の選定・開発ついては、「人権教育の指導方法等の在り方について」(文部科学省)に以下のように記されています。
この点で、保護者をはじめ地域の人々の生き方・考え方や歴史等豊かな地域教材を開発・活用することが重要である。
また、学習教材の選定・開発に際しては、児童生徒の発達段階を十分考慮するとともに、その内容を公正な観点から吟味する。さらに、例えば身近な事柄を取り上げる場合など教材の内容によっては、プライバシーの保護等にも十分配慮することが重要である。
これらのことについては、人権教育に限ったことではなく、他教科・領域などを含め、いずれの教育活動において普遍的でもあるといえます。
とくに特定の教科書がない総合的な学習の時間や特別活動などにおいての教材選定・開発に際しては、ここで示されている視点を十分に踏まえることが重要であると思われます。
プリント教材の作成
紙ベースの教材としての代表格ともいえるのが「プリント教材」ではないでしょうか。一般的に、業者・事業者から購入するドリル教材(書籍)とは異なり、教材や学習内容に合わせて、授業者が印刷し児童生徒に配布する形が取られます。
プリント教材の自作は、大きく以下の3パターンに分かれます。
Ⅰ 完全に自作(著作権は作成者である教員)
Ⅱ 書籍の市販プリント教材を複製(複製可能な書籍)
Ⅲ ダウンロード型の市販プリント(無償・有償)
教育効果を高めるためという軸がぶれないようにしつつ、多忙な業務時間の中で作成していくことを考えると、Ⅲのダウンロード型の市販プリント(無償・有償)を選択することは今後のトレンドになっていくのではないでしょうか。
プリント教材をWord(またはGoogle ドキュメント)で作るコツ
Ⅰ A4サイズ1枚に収まるように作る(ページ設定で確認)
Ⅱ 児童生徒の実態に応じて、フォント(書体・サイズ)を変える
Ⅲ 適宜、図表・イラストを入れる
基本的にはビジネス文書と大きな違いはありません。ただ、GoogleドキュメントにおいてはWordと遜色なく使うことができる一方で、用途によってはWordを選んだほうがいい場合もあります。縦書きや、漢字にルビをつける機能は、Googleドキュメントには標準装備されていないからです。これらを使うことが多いなら、無理に乗り換えることはせず、Wordを使い続けるのが賢明です。