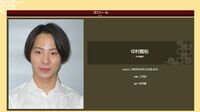GIGAスクール2年目「残念な学校、残念な先生」が広げるICT活用格差の行方 教育・校務のDXは意思決定を行うトップ次第
問題は残りの5割。おそらく先生たちが忙しすぎて、今までのやり方以外のものを取り入れる余裕がないということの影響も大きいとは思いますが、子どもたちも先生も十分にICTを活用する経験をしていないので、GIGAスクール構想による学習基盤の大きな変革が体感できていないのだと思います。
端末の持ち帰りをしている学校も、今はまだ全体の3分の2程度です。家庭に持ち帰ると何をするかわからない、と持ち帰りを禁止している自治体や学校がまだ見られます。それは子どもを信頼していない、信頼できる子どもを育てる教育が十分でないことと同じ。学校でICTを日常的に活用して学んでいれば、その延長で家庭でも望ましい活用の仕方をするものです。また、端末からのアクセスログは設置者である教育委員会では確認することができるはずです。失敗しない学習なんてありませんから、端末の持ち帰りもぜひ進めてほしいですね。
教育関係者の意識改革が「令和の日本型学校教育」を実現するカギ
──つまり、「令和の日本型学校教育」を進めるためには働き方改革が必須であり、校務のDX推進が2023年の課題になってくるということでしょうか。
校務改革はもとより、今後はデジタル教科書や教育データの利活用も進めていかなければなりませんが、それはある意味、環境整備の話にすぎません。授業、教育に対する大きなパラダイムシフトのために必要な学習環境がインフラとして整った今、新しい時代に向けた授業の形にどう変えるかという、学校の姿勢や先生たちの気持ちのほうが重要です。デジタル教科書が導入されても、残念な学校、残念な先生は、紙の教科書と同じ使い方しかしないでしょうからね。
デジタル教科書は24年度、小学5年生から中学3年生の英語に先行導入されることになりました。教育現場のアンケートでは算数・数学への導入も期待されており、いずれは国語や社会、理科、あるいは家庭科や体育などといった実技教科にもデジタル教科書は拡大していくことと思います。さらには副読本や資料集、AIドリルなどのデジタル教材も増えていくことでしょう。
こうしたデジタル教材は、それぞれ違う会社が作っているので、使用するたびに異なるIDとパスワードが求められます。いちいち入力するのも大変で混乱しがちなので、1つのIDとパスワードでアプリやWebサービスをひも付ける「シングルサインオン」という仕組みがあります。
その入り口になるのが、デジタル学習環境のハブの役割を果たす「学習eポータル」です。一部ではすでに実用化されていて、どの子がいつ、どの教材にアクセスして、どういう学習活動を行ったのかすべてログが残るようになっています。先生は一覧化された学習ログを見て個々の理解度、得手・不得手を把握し、それぞれの子に対してより細かな個別指導を行えます。
しかし、そのためには各教科書会社、教材会社の教育データが統一されていなければなりません。それが「教育データの標準化」といわれるものです。これが完成すると、先生の業務負担はかなり軽減されます。出席状況やテスト履歴、成果物なども記録されるため、それを見れば成績・評価が楽に行えるはずです。
アクセスログが残るから、不登校の子が学校以外のところでちゃんと勉強しているという証明になって、それを出席と見なすという流れにつながるかもしれません。また、クラウドツールを使うことで、保護者とのコミュニケーションも円滑になります。例えば、アンケート収集フォームを使えば面談日の調整が簡単にできますし、学校生活の様子の共有や急な連絡事項の周知にも活用できます。