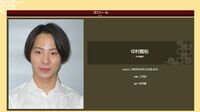GIGAスクール2年目「残念な学校、残念な先生」が広げるICT活用格差の行方 教育・校務のDXは意思決定を行うトップ次第

東北大学大学院情報科学研究科 教授、東京学芸大学大学院教育学研究科 教授
1964年熊本県生まれ。86年に東京学芸大学教育学部を卒業し、87年に東京都公立小学校の教諭として勤務。2009年東京工業大学より博士(工学)授与。文部科学省参与、玉川大学教職大学院教授などを経て、14年より現職。中央教育審議会・委員、同教科書・教材・ソフトウェアの在り方ワーキンググループ・座長、同義務教育の在り方ワーキンググループ・委員、文部科学省GIGAスクール構想の下での校務の情報化の在り方に関する専門家会議・主査、同教育データの利活用に関する有識者会議・座長などを歴任
一方、国が約5000億円もの予算をかけて端末を配ったのはただごとではないから、とにかく使ってみようと言ってやり出した学校では、子どもたちが入力、編集をはじめとする端末の基本操作はもちろん、クラウド上のツールの機能にも精通してきて、大人顔負けの使い方をしています。その結果として、学習活動は充実しています。
授業の内容も全然違います。これまでは「1603年、徳川家康が江戸幕府を開いた」ということを先生が説明し子どもたちが覚えようとするような浅い学びだったものが、今は「家康が江戸幕府を開けたのは何を克服したからか」とか「265年にもわたり政権が安泰したのはなぜか」といったことを、子どもたち自身に知識と知識をつなげて考えさせるような授業に進化しています。
これは子どもたちが情報活用能力を身に付け、さまざまな学習リソースにアクセスしながら学ぶことができるようになり、また先生も端末によって一人ひとりの進捗状況を可視化して個別支援しやすくなったからできることなんです。しかも、子どもたちはほかの子がどういうふうにやっているか、どういうまとめ方をしているかを見られるので、1つの課題でもやり方は多様で、自分は自分らしくやればいいということにも気づく。これは今の時代感覚として、ものすごく大切なことです。
──GIGAスクール構想の本質に気づいて、キャッチアップできている学校はどのくらいありますか。
ものすごくICT活用が進んでいる学校と、かなりいいところまで来ている学校と、残念な学校の比率は、僕の肌感覚では1:4:5くらい。すでに1割は、びっくりするぐらい変わっています。4割のところは、あと1年ほどでかなり変わると思います。ものすごく進んだ学校だって、2年前は試行錯誤の連続だったわけですから。あとは先生が音頭を取りすぎず、子どもにどのくらい任せることができるかというところでしょう。