複式学級で担任の負担軽減、青河小が導入した「AIロボット先生」の実力 「ユニボ先生」との学習であれば集中できる子も

一方で、課題もある。ユニボ先生の出題は比較的やさしいため、難易度のバリエーションがあると望ましいようだ。また、1体のユニボ先生の画面をのぞき込むのは3人が限度で、現在4人の児童がいる5年生での活用が難しい状況にあるという。
しかし、「GIGA端末と連動できれば、活用の幅が広がるのではないか」と、貞丸氏。実際、端末上でユニボ先生の指導を受けられるアプリは開発済みで、青河小では今年度中にGIGA端末にインストールする予定だ。そうなれば、児童は自分の端末を使い、授業中でも家庭でもユニボ先生による学習が可能となる。
また、現状はユニボ先生と子どもたちとのやり取りは音声のみで、子どもの声のかけ方によってはユニボ先生が音声を認識できない場合もあるが、タッチパネル機能も開発が進んでいる。この機能が搭載されれば、「より使いやすくなると思います」と貞丸氏は言う。
今後のAIロボット先生の可能性とは?
AIロボット先生の可能性について、貞丸氏は次のように期待する。
「将来的には、AIロボット先生と深い対話をしながら一緒に何かを考えて、探究していくようなクリエーティブな場面も見られるかもしれません。子どもたちがGIGA端末を手にしただけで調べ学習の幅が広がったことを実感していますが、進化したAIロボットが教育現場に導入されたらもっと面白いことになるのではと思います」
青河小では複式学級でユニボ先生が役立つことがわかってきたが、「ほかの導入先では、ユニボ先生は人間の先生ではうまくいかない子どもたちと相性がよいという面も見えてきました」と鈴木氏は話す。
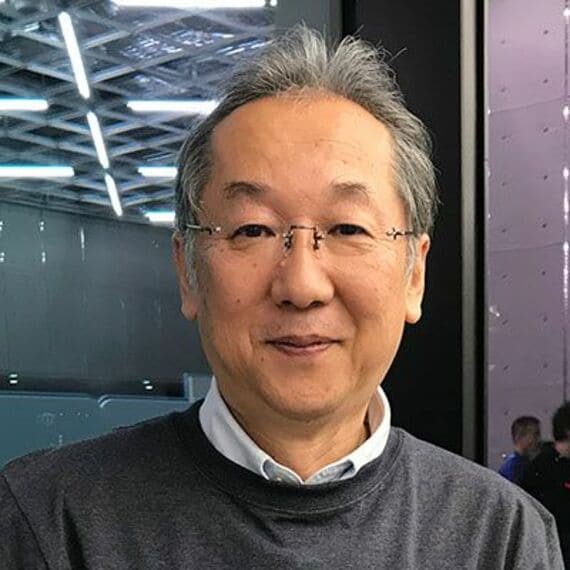
(写真:ソリューションゲート提供)
例えば、ある都内の民間学童クラブでは、勉強がつまらないとぐずる子や、2~3問の計算に1時間近くかかる子が、ユニボ先生が相手だと集中して勉強する姿が見られた。日頃「自分は理解できているから」と大人から教わることを嫌がるのに、ユニボ先生には「教えて」と言える子もいるという。
「学校の中には、いくら頑張っても授業についていけず、自信を失っている子がいます。でも、学び方は1つではないはず。従来の学校教育に合わない子をロボット先生で救えるのではないかと思っています。また、不登校児童生徒の学習支援や特別支援教育においても活用の可能性があると考えています」(鈴木氏)
ある自治体では、経済的に塾に通えない子どもたちでも学習できるよう、児童館にユニボ先生を置く案も検討されているという。AIロボット先生は、教員の負担軽減や多様な学びの保障に欠かせない存在となれるのか。さらなる進化に期待したい。
(文:田中弘美、編集部 佐藤ちひろ、注記のない写真:青河小学校提供)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























