気象予報士に聞く「気候変動や防災減災」を子どもたちに教える極意 将来の選択肢が広がるかも?進化する気象産業
子どもたちが自分で考え行動できるよう「答え」は教えない
――学校などでも講演活動をされていますが、子どもたちに気象について教える際に気をつけていることはありますか。教員へのアドバイスもあればお願いします。
防災意識の高まりを受け、防災気象情報と警戒レベルの意味や避難の種類・方法などはしっかりお話ししていますが、若い人たちには「避難の意味」を考えてほしいと思っています。
だから、自分で考えて行動できるように、一気に「答え」を教えないようにしています。例えば、手間はかかるのですが、まずは自分がいるエリアの危険度をハザードマップで調べるところから始めたりします。

なぜ災害が起こり、どんな事態が発生し、自分にどのような影響が及ぶのか。なぜ自分は逃げなければいけないのか、どう行動すれば安全が保たれるのか。そういったことを各自が追究できるような進行で伝えることを心がけています。
先生方の防災・減災教育もこうした形がよいのではないでしょうか。気候変動が題材である場合も、猛暑日や猛烈な雨が増えているなどの事実を伝えるにとどめ、原因や対策は子どもたちに考えさせる追究型、探究型がよいと思います。「プラスチックをなるべく使わない」など具体的な方法を先生が教えても、それは押し付けになり何も身に付きません。子どもたちが自分で選択肢の意味を考え、自分ができることを採用することが大事です。
また、とくに防災などは意識が高まったとしても続かなくなってしまうことが多いので、少しでも興味を持ち続けてもらえるよう、天気や気象の面白さを伝えるようにしています。社会課題を考える入り口としてまず、気象を好きになってほしいなと思っています。
例えば、私は気象の勉強を始めた当初、『楽しい気象観察図鑑』(武田康男著/草思社)など気象の写真集をよく眺めていました。気象の変化によって変貌する自然の姿は本当に美しく、見ていて飽きません。そうした本には大抵、解説も付いているので、楽しみながら「気象のサイエンス」を知ることができます。
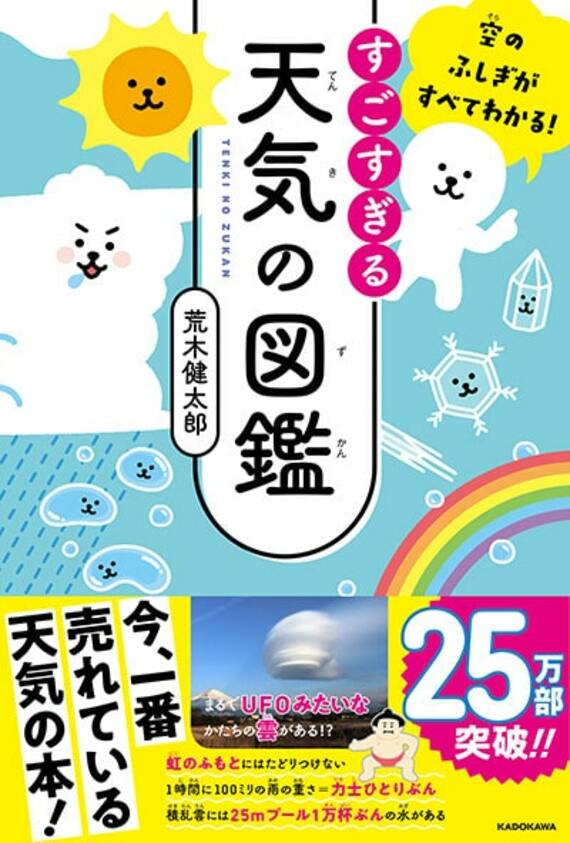
すでに大ヒットしていますが、私が専門知識の伝え方などをご指導いただいている雲研究者・気象庁気象研究所研究官の荒木健太郎さんのご著書『空のふしぎがすべてわかる! すごすぎる天気の図鑑』(KADOKAWA)はとくにお薦めです。「なぜ雲に乗れないのか」「虹に出合う方法」といったさまざまな切り口で、気象の仕組みや災害問題について子どもから大人までわかりやすく学べます。
そういったツールも使いながら、子どもたちや学校の先生には気象を楽しんでほしいです。とくに子どもたちには、「空がきれいだな」「あの雲、動物みたいでかわいいな」といった興味・関心や空想をきっかけに、たくさん疑問を持ってとことん調べてほしい。そこが気候変動や自然災害といった社会課題を考えていく入り口になると思っています。
(文:國貞文隆、注記のない写真は佐々木恭子氏提供)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























