8年連続増「SNSいじめ」が加速させる不登校 不登校支援の肝となるのは「保護者支援」だった
ただ、今は多くの学校でもICT教育がスタートし、公的支援もアップデートできる局面にあるはずだ、と今村さんは苦言を呈する。
「私たちの不登校支援は現状、ホームスクーリングのツールを提供していることになります。しかし、本来は学校で不登校を生まないよう、未然防止として、一律の学び以外の対策も取れるのではと思います。例えば図書館など、教室とは別の場所でパソコンを使い、授業を受けることも可能でしょう。そうした選択肢を学校でもっと増やしていくこともできるのではないかと感じています」
すでにいくつかの自治体では、ICTを使った新たな不登校支援を始めている所もあるという。
「学校も、今後は何事も自前で行うという発想をなくしたほうがいいかもしれません。オンラインを使えば、人材のリソースを集めることも容易になります。先生たちが自前でやろうとすると負担が大きくなりがちです。例えば自治体によっては、校区ごとにスクールソーシャルワーカーを1人配置しています。しかし、校区の生徒数が1000人いれば、それを1人で担当することになり、現実的には丁寧に対応するのは無理があるでしょう。それがオンライン上のリソースを使うことで、より的確に対応することができるようになるのではと思います」
そう語る今村さんは、不登校の子どもの保護者にもこうアドバイスを送る。
「不登校は子どもが家庭の中で親としか話していない、という状況が生まれやすい。私もそうですが、親子で話すとつい感情的になってしまうことがあります。ですから、不登校の子どもには、できる限り家族以外の人と話せるような環境に触れさせることも大切になってきます。そのためにもオンラインという手段がある。親も子も1人で苦しまず、私たちのような外部のリソースも活用し、1人で抱え込まないでもらえればと思っています」
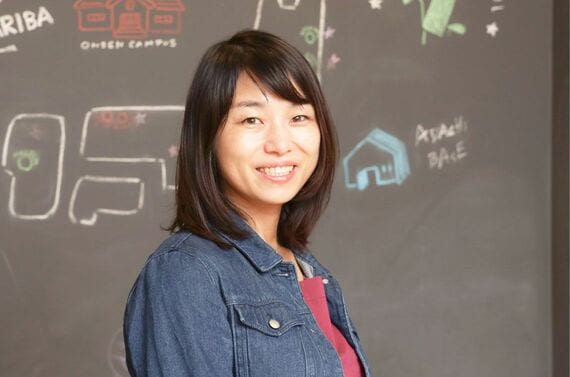
1979年生まれ。慶應義塾大学卒。2001年にNPOカタリバを設立し、高校生のためのキャリア学習プログラム「カタリ場」を開始。11年の東日本大震災以降は子どもたちに学びの場と居場所を提供するなど、社会の変化に応じてさまざまな教育活動に取り組む。「ナナメの関係」と「本音の対話」を軸に、思春期世代の「学びの意欲」を引き出し、大学生など若者の参画機会の創出に力を入れる。ハタチ基金 代表理事。地域・教育魅力化プラットフォーム 理事。中央教育審議会 委員。経済産業省産業構造審議会 臨時委員。認定NPO法人カタリバ 代表理事。カタリバ(https://www.katariba.or.jp/)
(写真:カタリバ提供)
(文:國貞文隆、注記のない写真:buritora / PIXTA)
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























