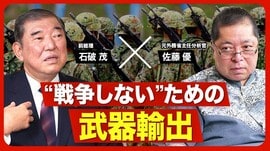そうですね。しかし受験というのは、合格したら終わりではありません。むしろ合格したところからがスタートです。第1志望の学校に落ちて、第2、第3志望の学校に行くことになる場合もあるでしょう。その場合にも、ランキング重視で選ぶとそれ以外に理由がないから子どもにとって通うモチベーションがなくなってしまう可能性があります。
まずは、親子で探索してみてください。学校選びを親子で一緒に楽しみながらやってみる。子どもが好きなことにひも付けて学校を見ると、より子どもが主体的に学校を選び、その先の学びに取り組むことができるはずです。いろいろな学校を見て、選択肢が1つではない、たくさんあるんだということを知ることも重要です。
「近所の公立の学校もあるし、そうでない学校もあるし、いろいろな学校があるんだね。学校って、何が違うんだろうね」「〇〇ちゃんが受験するんだって。どんな学校なのか見てみようか」というように、偏差値ではなく学校自体に興味が湧くような声がけが重要です。
遠足に行くような気分で学校見学に行ったり、オンラインで学校のことを調べてみるのもいいですね。「この学校に行ったらこういうことがありそうだよね」と、学校自体や学校生活に興味が湧くように導きながら、子ども主導で一緒に探索して、子どもの好奇心を導き出すような接し方をしましょう。
受験はただの通過点、合否に重きを置かないで
――ほかには、どんなことに気をつけるべきですか?
親として最も重要なことは、「合否にフォーカスしない」ということです。合格しても不合格でも人生は続いていきます。子どもは合否の先を生きなければならないのです。
そのために重要なことは、受験が終わったあとに、学校生活で何を学びたいのか、何をなし得たいのかということにフォーカスすることです。第1志望の学校に受かったときはもちろん、第1志望の学校ではないところに通うことになっても、今までの努力を認めて褒め、その先の学校生活をイメージできるようにサポートしてあげることが重要だと思います。受験というのは合格するために挑むものですが、合否だけにフォーカスすると、たとえ合格してもそこで燃え尽きてしまう可能性もありますし、不合格になれば、すべての努力が否定されたと感じてしまいかねません。それでは「自分はダメだ」と、自己肯定感をはじめとする非認知能力は下がってしまいます。
ですから、受験では合否という結果ではなく、まずは自分軸での学校選びに始まって、最終的に通う学校が決まるまでのプロセスにフォーカスしましょう。そうすれば受験を通して自己肯定感、好奇心、主体性、レジリエンスやグリットといった非認知能力を育むことができます。それは確実に合否の先を生きる力になって子どもを支えてくれるでしょう。
――自分で選ぶことから始める受験だからこそ、合否にかかわらず子どもは自分の人生を切り開いていけるのですね。
「この地区ではこの学校がナンバーワンだからそこに行く」というのではなく、「なんでその学校に行きたいのか」ということを自分なりに考えて受験するという行為そのものが、非認知能力を育む入り口になります。そのためにも子どもの好奇心を導くような接し方が大切なのです。