中教審の「学びの成果についての理解」が浅い
2点目は、新たな学びの成果とは何なのかについても、あいまいである。
今回の案の中核となっているのは、研修履歴を管理、活用していくことであろう。中教審のまとめによると、「学びの成果が可視化(何が身に付いたのか自ら説明できる状態)されることにより、教師は自らの『現在の姿』を適時適切に更新することが可能となる」といった言及がある。
学びの成果とは「何が身に付いたのか自ら説明できる状態」なのだろうか。
例えば、私は学校の組織マネジメントや働き方改革について研修講師をたびたび務めているが、「研修を受けて、働き方改革の必要性がよくわかりました」といったアンケート結果はよく頂戴する。だが、これは学びの成果ではない。研修の主催者も私も狙っているのは、研修内容で参考になったところがあれば、それを活用して、学校などで行動、変化が起きることだ。
つまり、文科省などの案は、研修を受講したことと、その内容を習得、活用したかは別であるはずなのに、受講したことだけを重視しているように見える。専門用語を含むが、これは研修の「転移」と呼ばれる問題で、研修を受けたかどうかよりも、仕事、成果につながっているかどうかが問われなければならない。
もちろん、業務に直結することだけが教師の学びではない。例えば、歴史や哲学を学ぶことは、自由の意味・意義を考えるうえで重要だろう。つまり、研修等の目的、狙いによって成果は変わるが、少なくとも、「研修を受けましたよ」が成果ではない。
以上述べた2点について、もう少し突っ込んだ議論と制度設計をしておかないと、教員免許更新制に代わる新たな仕組みができたとき、学校現場はどうなるか。校長などから「あなたは毎年ちゃんと研修を受講していますね。この調子で頑張ってください」といった声かけがあるくらいの運用になるのではないだろうか。現に、研修受講履歴を記録・管理している都道府県教育委員会は、今でも76.5%(中教審「教員研修履歴の管理等に関する調査結果」の幼・小・中・義務において)ある。それで豊かな学びになっているだろうか。十分になっていないとすれば、それはポータルなどがないせいではなく、もっと違うところに問題があるのではないか。
「主体的で対話的で深い学び」とは新しい学習指導要領で児童生徒に向けて言われていることだが、教師と学校組織が「主体的で対話的で深い学び」を進めていくために、どんなことが必要か、美辞麗句を並べるだけになってはいけない。
(注記のない写真:tadamichi / PIXTA)
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






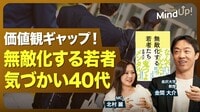


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら