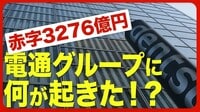読み・書き・計算「基礎学力は学習アプリで」の実際 東京学芸大と岡山・津山市「モノグサ」で実証事業
参加した生徒からも「親に言われて参加したが、受けてよかった」「わからないところが、わかるようになった」「わからなかったところについて、大学生とコミュニケーションを取るうちに、わからなかったポイントがわかり、ここをつぶしていこうというのが見えた」など評判がよかったが、課題もあった。「回線が遅い」「パソコンの接続が難しかった」「紙のように計算の過程が書けずに困った」など、オンラインならではの課題が多く、今後はネットワークの整備を含め、Wi-Fi環境のいい場所で実施する、また地域の人材を活用して対面で指導を行うことも検討したいとした。
学校と家庭、地域、企業が協働して教育課題の解決へ

東京学芸大学 副学長
東京学芸大学で「未来の学校みんなで創ろう。プロジェクト」を進める副学長の松田恵示氏は、「昨今は『思考力・判断力・表現力』といったコンピテンシーの育成がいわれているが、基礎を学ぶからこそ思考が広がる。資質能力と基礎学力は、一体となって学ぶことが重要」と強調する。ただ、基礎を身に付けるには継続して取り組むことが大切で、苦労している子どもも多く、学習意欲も下がりがちだという。
その点、「モノグサ」のようなベーシックな問題やテストが実装され、子どもの実情に合わせて繰り返し取り組むことができ、学校や先生の要望を反映した問題を搭載できるアプリは、個別最適な学びの実現に有効だ。
松田氏も「記憶の定着にフォーカスしていて『モノグサ』は基礎の定着が得意。ただアプリがあれば何でもできるわけじゃない。今回の実証事業のように学生のほか、先生や保護者が伴走者になってもらい確実で効果的な学習に取り組んでほしい」と話す。
こうしたAIをはじめとするICTを活用した学びの支援は、今後も期待が大きい分野だ。だが、コロナ休校中のオンライン対応でも見られたように、私立と公立の差は今は大きく開いているように見える。
東京学芸大学の「未来の学校みんなで創ろう。プロジェクト」に公教育の変革を掲げるのも、「持てるものはさらに富む、持たないものはさらに貧しくなる」(松田氏)という危機感があるようだ。「1人1台端末」の活用は始まったばかりだが、手綱を緩めることなく、学校と家庭、地域、企業が協働することで教育課題を解決する方法を模索し続けてほしい。
(文:編集チーム 細川めぐみ、写真:すべてモノグサ提供)
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら