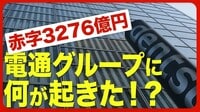読み・書き・計算「基礎学力は学習アプリで」の実際 東京学芸大と岡山・津山市「モノグサ」で実証事業
現在、さまざまなプロジェクトが進行中だが、AIやAR/VRなどICTを活用した学習環境の整備は大きな柱となっている。津山市の実証事業は、学校と地域などが協働し小中学校での基礎的な学力の育成をテーマに研究を行う「基礎学力育成社会システム開発プロジェクト」の1つで、津山西中学校の3年生を対象に7月末から8月にかけて1回60分、全5回の授業が行われた。

学習アプリ「モノグサ」を用いて数学の平方根を学ぶというものだが、面白いのが東京学芸大学の学生が、家庭教師のようにオンラインで生徒に指導を行うところだ。
東京学芸大学からは学生が5名、津山西中学校からは生徒10名が参加し、Zoom上で学生1人に対し中学生2名というグループをつくって指導が行われた。1回目と2回目は津山西中学校の教室に生徒が集まって、3回目以降はGIGA端末を持ち帰って生徒それぞれの自宅で実施。平方根の計算に関する課題を「モノグサ」で繰り返し解くと同時に、「モノグサ」の小テスト機能を使って、苦手や理解が不十分なところを明らかにしながら、間違えた問題の解き方を生徒から聞き取って学生が解説するなど手厚い指導を行った。

津山市教育委員会 学校教育課
9月末に行われた実証成果発表会で、津山市教育委員会 学校教育課の梶並公人氏は「津山西中学校では、学力状況調査の結果から基礎学力の定着がいま一つ」だと感じていたと話した。とくに小学校高学年の算数の単元、また英語では授業で得た知識の活用に課題があると分析していたが、家庭学習で補うにも十分にカバーできずにいた。「理解が不十分なところがあっても、授業はどんどん進んでいくため、学習意欲の低下にもつながる。既習内容を振り返り学習しつつ、基礎学力を定着、学習意欲を向上させることができないか」(梶並氏)と考えていたのだ。今回の取り組みは、こうした課題解決につながる実証事業だという。

津山市教育委員会 教育総務課
津山市教育委員会 教育総務課の歴舎潤氏は「分数の掛け算ができていないから、ここをやろうなど、どこに戻って学習すべきかがわかるのがいい」と話す。今回は「モノグサ」を使うことでテストの採点や学習状況の分析は省力化しつつ、苦手なところに取り組むなどの声かけを学生から行って、生徒のモチベーション維持を図った。「アプリがいくら有能でもやらないと学力は上がらない。1人でやれるならいいが、やれるようにしてあげるのが学習サポーターの役割」(歴舎氏)という。この実証事業では、短期間にもかかわらず、10人中8人が初回テストから成績が上がったという。