国内外から生徒が集まる「島の学校」の正体 統廃合寸前の危機から復活遂げた隠岐島前高校
――魅力化の取り組みの中では、アンケートなどで幾度も課題をヒアリングされています。「島前高校には、刺激や競争がない」「多様な価値観との出合いがない」「新しい人間関係をつくる機会がない」などの声を基に全国から入学者を募る「島留学」制度も作られました。普段から、自らの弱みをさらけ出して改善するということを意識されていたのでしょうか。

岩本:僕は基本的に自分の弱いところを見せられないし、頑固なのか、割と自分のスタイルを変えられないところもあって。吉元さんには当時、「つらい」「苦しい」「困っている」というのを見せていかないと、人は共感しないし応援したいと思わないと言われました(笑)。そこからは意識して弱音を吐いたりとか、いろいろ指摘してもらって、自分自身を変えていく努力をしましたね。
吉元:人の悪口を言ったほうが、人間味があっていいよというアドバイスもしたんだけど、岩本くんは最後までできんかったね(笑)。つねに、自分たちが間違ってるんじゃないかと見直す姿勢を崩さなかった。実際、自分が正しくて相手が間違っているという考え方で先生と対立してもダメだし、教育委員会と対立してもダメだし、3町村で対立してもダメだし、っていうことで「三方よし」を合言葉にしていたよね。
岩本:確かに「三方よし」は合言葉なのか理念なのか、キーワードでしたね。吉元さんはそういうふうに言ってくださるけど、僕は基本的に自分が正しいと思っている人間で(笑)。自分が正しくてほかの人が間違っていると思っていると、人を批判して、何でわかってくれないんだ、あいつらはダメだという話になってしまう。それで何度も失敗しました。「自分の見えていないものがあるとしたら、どの部分なのか」を考えて自分から変わっていかないと、うまくやれないということを痛いほどわかって、改善していったというのはあるかもしれません。
――失敗して反省し、改善するといったサイクルは、どのように回されていたのでしょうか。
濱板:作戦会議を頻繁にしていましたが、「誰が・どのタイミングで・どんなシチュエーションで」その話を持っていったらいちばん有効かなどを話し合っていましたね。実践して、失敗したら、次の作戦を練っての繰り返し。最初は苦痛だったけれども、だんだん楽しくなってきて(笑)。
豊田:いわゆるPDCAを、本当に早く回していましたね。パーフェクトな計画を立てるよりも先にDOをやって、そこから振り返る。PDCAのAは「謝る」だっけと思うほど、失敗しては謝っていました(笑)。いろんな利害関係者たちが、この打ち手をどう見るだろうと思いを巡らせながら、「確かにこれは学校の先生が感情的にいい気持ちがしないからやめようか」とか、そういうことの繰り返しでしたね。
――そんな魅力化の取り組みを通して、結果的に3町村の関係はどのように変わったと思われますか。
吉元:島前高校の島留学や島親制度なんかを通して、地域の方々と信頼関係を構築できるようになったね。島全体を学校に見立てて、地域の方々が島留学に来た生徒の「島親」として島の仕事を教えたり、一緒に自然体験したりと協力し合ったことで、3町村の人たち皆で喜びを分かち合えるようになった。
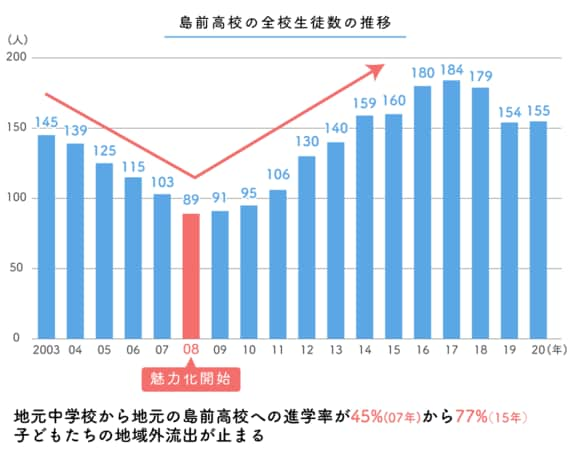
岩本:日本全国から中高生の参加者を集め、島内3町村の中高生と共に、島の「ヒト」の魅力を堪能する旅企画「ヒトツナギツアー」の取り組みも、3町村で1つのことをやっていく最初の大きな一歩になったと思います。高校生が一生懸命、島前の魅力を体感してもらえる旅とは何かを模索する中で、地域の方々も協力してくれました。

濱板:最近は、島前高校を選択肢として考える生徒や保護者の方が圧倒的に増えたと感じています。とくに島前高校は海士町に位置していることから、西ノ島町や知夫村からの入学率が低かったんですが、「海士町の高校」というより「島前の高校」と認識してもらえるようになった。学園祭の活動を一緒にするなど、地域住民の共通の話題ができたことも大きいと思います。
豊田:直接地域の方から聞いたところで言うと、隣の島に負けたくないというライバル心はありつつも、島前高校のためなら一緒に頑張りたいという気持ちが醸成されつつあるようです。当初は「島前」という単位で動くことが少なかったけど、今は教育だけでなく、福祉や医療、観光の分野などでも、「島前」として一緒にやっていこうという雰囲気になっていますね。
岩本:島前高校で3年間過ごした生徒たちって、島外からの多様な生徒たちと地域のために協力して物事を成し遂げるという貴重な体験を通して、それぞれの個性を認めて活かし合う力を身に付け、さらに「島前」というつながりを持って卒業していますよね。だからこそ、彼らがUターンやIターンなどで帰ってきたときには、島前地域はさらに変わっていくんじゃないかなと思います。
吉元:そういえば、去年Uターンしてきて海士町役場に勤めている24歳の子がいるんだけど、家督会(あとどかい)という、いわゆる島前高校のOB会をつくったり、大学生を中心とした就業体験制度「大人の島留学」を実施したりしているよね。
豊田:その企画を担当している子は、海士町生まれ海士町育ち、海士町の役場に勤めていて、「海士町のために」となってもいいはずなのに、「大人の島留学は島前3町村の枠組みでやりたい」と言っているんですよね。「島前のために」というよりは、「島前高校で共に過ごした西ノ島や知夫村の同級生のために」という感覚に聞こえます。






























