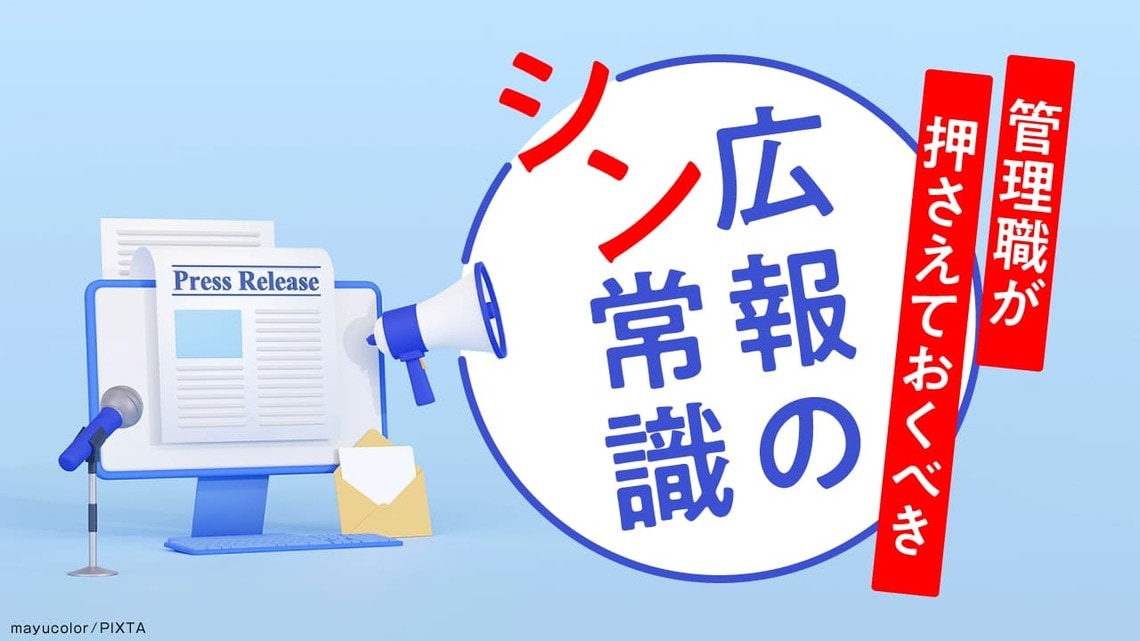
連載第5回は、危機対応のフレームワークについてお話をしたいと思います。
危機というのは、そう簡単にはやってきません。実際、ほとんどの会社の広報担当は危機対応の経験をしたことはありません。セミナーに参加したり書籍を読んだりしても、得られる情報は一般論に終始しがちです。というのも、危機対応の成否を握るようなノウハウは、個別の事例のかなり踏み込んだところにしか存在しないためです。
危機対応の内部情報などは、どの会社も社外秘扱いです。いくらネットを検索してもろくな情報に行き当たりません。情報共有は関係者限りとすることが多く、社内でも知っている人は少ない、というのが実情です。ネットの情報を学習している生成AIに尋ねてみたとしても、毒にも薬にもならないような回答しか得られないと思います。
5つのポイントを押さえる
とはいえ、絵を描く際になにもない白紙に描くよりも補助線を何本か引いたほうが失敗がないのと似て、広報対応にも一種のフレームワークのようなものがあります。以下の5つのポイントは筆者が諸先輩から習ったものであって、一般的なものかどうかはわかりません。
しかし、実際に筆者はこのフレームワークで何回も危機対応を乗り切ってきました。広報は学問ではなく実務です。「実際に役に立った」という事実は大きいと思います。
具体例で説明します。しかし、実際に起きた事件を取り上げると差し障りがあるので、ここでは私が好きな歴史の話に例えます。古代を舞台としたフィクションで説明します。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら