
消費者心理の厳しさは継続している
――不作によるコメ価格の上昇など食品価格の高騰が続いています。どのようなスタンスでトップバリュを推進したのでしょうか。
消費者心理の厳しさは継続しており、トップバリュの開発体制にも影響は大きい。先日、地元のスーパーに出かけたところ、青果コーナーにあったキャベツの外側の葉を捨てる箱に「(箱に捨てられた葉の)持ち帰りは1人2枚までにしてください」と書かれてあった。
価格が高くなりすぎて、「通常は捨てるこのような葉を持って帰らないと野菜を食べられない消費者が出てきているんだ」と思い、とても切なくなった。そうした消費者を前に、私たちはどのようにすると安く商品を提供できるのか、ということを考えないといけない。
昨年は里芋の相場が高騰する中、通常捨てられていた「親芋」部分を使用したポタージュなどを販売した。本来捨てられている食材を探して価値に変えることができれば、生産者の収入にもなるし、単なる値上げを回避することもできるかもしれない。こうした商品開発は今後も強化していく。
一方で、特定の商品の価格が上がったとしても、消費者は自然と別のものを探そうとする。誰しも食べなければ生きていけないからだ。その代替消費を捕らえることも重要だ。









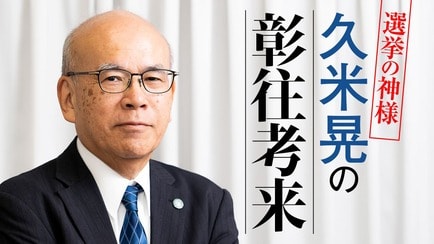






















無料会員登録はこちら
ログインはこちら