ドルトン東京学園、暗記中心の受験対策と一線画す「異色の数学」で生徒に変化 「おもしろい授業をするのがいい先生」が原動力
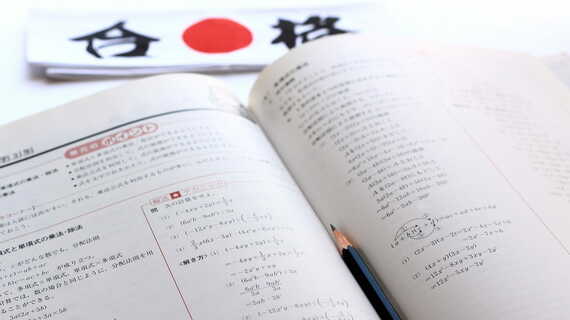
暗記数学的な指導が中心、「考える力」を軽視
「暗記数学」という言い方がある。解法パターンを暗記して問題を解く勉強法のことである。数学といえば「考える学問」という印象だが、暗記数学では考える要素が少なくなってしまう。
現行の学習指導要領の基本的な考え方について、文部科学省はホームページでこう説明している。「いまだかつてなかったような急速かつ激しい変化が進行する社会を一人一人の人間が主体的・創造的に生き抜いていく」ことが必要とされており、そのために「自ら学び、自ら考え、主体的に判断」する力をはぐくむことが教育に求められている、と。
今の子どもたちには「考える力」が不足しているからこそ、なおさら必要性が強調されているともいえる。その不足している原因の1つが、暗記数学にあると考えられる。
暗記数学になってしまっている理由を、ある私立高校で数学を教えている教員は「やはり受験です」と言った。総合型や学校推薦型といった年内入試が増えるなど、大学入試にも変化はみられるものの、まだ主体は一般入試であり、そこでは点数が重視される。
限られた試験時間の中で多くの点数を取るには、余計なことを考えないで求められている答えを早く出さなければならない。そのために効率がいいのは暗記数学である。だから高校、そして高校受験を控える中学でも、暗記数学的な指導が中心になってしまい、結果として「考える力」が軽視されることになっている。
「マイナス×マイナスは何になるか、それはなぜか」を3時間やる
そういう中にあって、ドルトン東京学園中等部・高等部で行われている数学の授業は暗記数学ではない。生徒1人ひとりの自主性と創造性を育むドルトン・プランの実践校として2019年に誕生した同校の数学指導は、興味深い。

(写真:前屋氏撮影)
八島容子氏は現在、4年生(高1)の数学を担当しているが、この4年生が1年生(中1)のときから担当している。1年生のときには、こんな授業をしたという。
「『マイナス×マイナスは何になるか、それはなぜか』を生徒たちで議論する時間を取ったら、みんなが納得できる結論にたどりつくまでに、結果として3時間かかりました」
3時間続けての授業だったわけではなく、1日1コマずつを3日やったのだ。2日目でだいたいみんなが納得できる結論になり、3日目は総まとめをするつもりだった。その3日目に、1人の生徒から、自分で調べてきたことがあるのでみんなに説明したい、との申し出があった。
その内容が、大学レベルの「群論」という現代数学の領域にまで踏み込むものだったという。誰かに教わってきたわけではなく、自分でネットなどを使って調べてきたのだ。大半の生徒には難しい内容だった。「一生懸命かみくだいて説明してくれましたが、聞いている生徒たちは、半分以上は理解できなかったと思います」と、八島氏は笑った。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら