パパ先生なら知っておくべき「男性育休・時短勤務」制度取得の裏側 「時間がなくても幸せ」経験者が断言する理由は
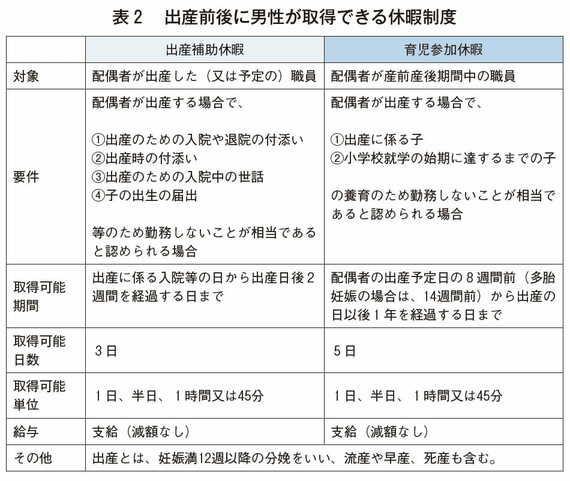
夫婦の役割分担
活用する制度を決めるとともに、佐賀井氏は夫婦で「子どもの送り迎えについては、事前に分担を決めておくとスムーズ」と話す。とくに育休明けの4月は注意が必要。子どもの慣らし保育期間と学校の新年度が重なるため、お互いがいつどのようなスケジュールで動いているのかを可視化させることが大切になるようだ。
働き方の工夫
一方で、制度を利用して時間内で仕事をするには、当然ながら工夫が必要だ。かつて21時から始まる会議や何十連勤といった働き方を経験してきた森氏は、現在ではつねに“時間対効果”を意識しているという。
「教員の仕事は、効率よりも『情熱』や『思い』に重きを置くきらいがあります。しかし、限られたリソース(時間や人手)の中で物事を進めるには取捨選択が欠かせません。教員によって意見が異なる取り組みは、エビデンスを参照して、より効果が高いと思われるものを選んで実践するようにしています」
佐賀井氏も独身時代は21時まで働くのが当たり前だったというが、今は日々のタスクの重要度を見極めて働いていると語る。
「教育活動には、しなければならないこと(=must)と、したほうがいいこと(=better)が存在します。例えば、生徒との対話はmustですが、面白い学習プリントを追加で作る作業はbetterです。パパ先生は家庭との両立を考えたときに、思い切ってbetterを切り捨て、mustに注力する必要があると感じています」
取捨選択の基準として佐賀井氏は、「学級担任である前に学校の人員である」ことを意識しているという。全職員・生徒に影響が出る“学校全体のための仕事”を最優先に位置づけ、次に“学年全体のための仕事”、最後に“クラス全体のための仕事”をすると決めているそうだ。
フィンランドは夫婦で育休取得!パパ先生が考える制度の改善点
「異次元の少子化対策」を掲げる岸田文雄総理大臣は、2023年3月17日の記者会見において、出生時育児休業給付金の水準を引き上げる方針を示した。
「子育て世帯への経済的支援は必須です。教育政策とそれ以外の政策の効果を比較し、教育政策への投資の高さを示す研究もあります(※2)。日本の出生率は低下していますが、2人、3人と産むことの壁を取り払うためにも、教育事業には投資してほしいと切に期待しています。また、例えば2人目以降の妊娠で妻のつわりがひどい場合、夫が上の子のフォローをしなければなりません。妻の妊娠期間中、男性が気軽に育休を取れるように、多子世帯の特別休暇の増加や小学3年生までの短時間勤務の拡大など、制度をさらに充実させることも一つの手ではないでしょうか」(森氏)
※2「成長政策の経済分析」経済産業研究所(RIETI)森川正之(2013)など
男性の育休取得を当たり前のこととして根付かせるためには、男性の育休取得率が約8割に上るフィンランドの制度が参考になると佐賀井氏は言う。
「フィンランドの育休制度では、男性と女性に7カ月ずつ平等に育休を与えると決まっています。日本もこのくらい思い切った制度を打ち出さないと、なかなか男性の育休取得率は上がらないのでは……。パパ先生の育休取得を普及させるには、複数の担任で複数のクラスを見ていく、ゆくゆくは教員全員で見ていくマインドが浸透することも重要でしょう」































