実は東大では、昔から「知識ではなく思考力を問う」入試問題を出題していました。「カボチャはなぜニュージーランドから輸入されているのか答えなさい」とか「カードゲームのブラックジャックで勝つ確率は?」とか、そういう問題が出題されていたのです。
実は先ほどの「なぜ、朝焼けがきれいだと明日は雨になりやすいのか?」という問いは東大の入試問題でもあります。こういった「本質的な思考力を問う問題」を、東大の入試問題も使いながら、東大生や東大の入試問題に詳しい予備校講師の人などからもお話を伺って、授業のコンテンツを開発しているのです。
こうした問いに早い段階から触れていれば、今後の「思考力を重視する」傾向の中でもしっかり戦っていける能力が身に付けられるのではないかと考えています。
この事業を本格始動したのは今年からなので、まだ実績はありませんが、試験的に授業を受けてもらっていた何人かの生徒は、今年の共通テストでもかなりの高得点(全科目を通して80〜85%)を取っていて、手応えを感じています。
問いに対する答え方の「型」をしっかり教える
僕が実践してみて感じたのは、「生徒は、誰かからきちんと教わらないと、なかなか思考力を身に付けることは難しいんだな」ということでした。
例えば、「新宿駅は、世界一乗降客数の多い駅なのはなぜか?」という問いを投げかけたときに、中学2年生の生徒の中には、「日本の人口が多いからじゃないですか?」と答える生徒もいました。
これって、いろいろ甘いポイントのある答えですよね。しかし、誰からもこの解答が甘いということを教わっていない、また指摘された経験がないと、どこがおかしいのか認識できないと思います。
だからこそ、この講座ではこういう問いに対する答え方の「型」をしっかり教えていきます。そこでまずは、「事実」と「意見」を切り分けて考えてもらいます。
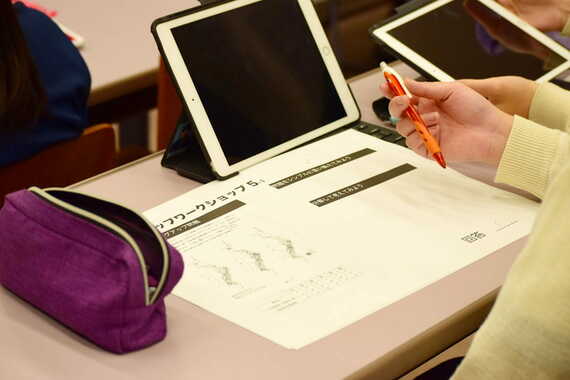
「人口が多い」という言葉は、物事を深く考えるうえではあまり適切なものではありません。なぜならそれは「意見」だからです。「事実」は、誰の目から見ても明らかなデータのことです。それ自体には何の色もなく、ただの数字でしかないもののことを指します。
対して「意見」は、その事実から一歩進んだ主観的なものです。ただのデータ・客観的なものとは異なります。そして「事実」としての言葉と「意見」としての言葉は異なります。






























