STEAM(スティーム)教育とは?STEM教育とどう違う?学校や家庭での取り組み事例を紹介
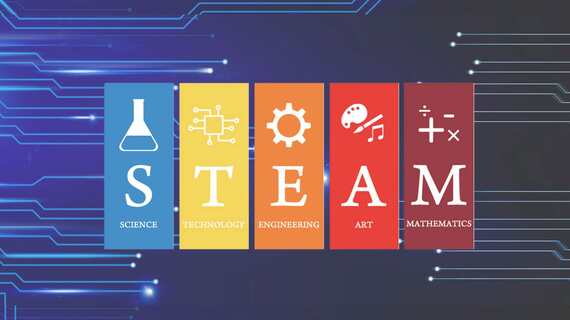
STEAM教育とは?
STEAM(スティーム)教育とは、Science(科学)+Technology(技術)+Engineering(工学)+Mathematics(数学)にArts(芸術・教養)を加え、その頭文字を取った言葉です。2006年にアメリカの技術科教師ジョーゼット・ヤークマン氏によって提唱されています。
現在、AI(人工知能)が劇的に仕事や生活のあり方を変え、求められる人間の仕事は単純作業から独創的な創造性と高い生産性の業務へと変わりつつあります。将来どんな職業に就こうとも、このScience、Technology、Engineering、Mathematicsの教養が必要となり、人間の特徴である創造的な分野「Arts」を掛け合わせ、総合的に学ぶという教育です。
STEAM教育が提唱された背景の1つには、情報科学やテクノロジーの進化に伴い、これらに対応するすべての人への理数系の教育が急務となっていることが挙げられます。しかし、STEAM教育の本質は「自発性」「創造性」「問題解決能力」といった能力の育成で、必ずしも理数系の教育が目的ではありません。
STEAM教育の歴史と目的
STEAM教育の歴史
STEAM教育はもともとSTEM(ステム)教育から始まりました。
STEM(STEAM)教育とは、1990年代に国際競争力を高めるため科学技術人材の育成を目的とした教育政策として注目されてきたといわれています。
このSTEM教育が変化したものとしてSTEAM教育が生まれ、STEAM教育はアメリカのオバマ元大統領が演説で述べたことにより注目されました。
これをきっかけに多くの著名人が賛同し、STEM(STEAM)教育は世界に広がったのです。
STEAM教育の目的
5つの領域の知識・技術を関連づけ、社会の課題を解決できる人材の育成を目的としています。
STEM教育との違い

最初に始まったSTEM教育には、Artsが含まれていません。物を作る際には科学の知識や技術に加え、デザイン性も重要です。さらに、このArtsにはリベラルアーツ(教養)も含まれます。人間が生きていくうえでの根本的なものの考え方や見方、知識などを指しています。独創的かつ創造的な考え方と、教養を養うためにSTEMにAが加わったと考えられます。
STEAM教育と文部科学省
文部科学省では、「STEAM教育などの各教科等横断的な学習」について下記のように推進しています。
「AIやIoTなどの急速な技術の進展により社会が激しく変化し、多様な課題が生じている今日、文系・理系といった枠にとらわれず、各教科等の学びを基盤としつつ、さまざまな情報を活用しながらそれを統合し、課題の発見・解決や社会的な価値の創造に結び付けていく資質・能力の育成が求められています。
文科省では、STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)に加え、芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲でAを定義し、各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていくための教科等横断的な学習を推進しています」
STEAM教育を取り入れた事例
小学校での事例

国の「GIGAスクール構想」により、子どもたちは1人1台の端末を用いるようになり、オンラインでつながれるようになってきました。そのため先生が教材ファイルを共有し、また子どもたちが共同で書き込んだりすることも珍しくなくなってきました。






























