
発電事業者は「濡れ手で粟」の収入
――容量市場の第1回入札結果が公表されました。どのように受け止めましたか。
約定価格は発電容量1kW当たり1万4137円と、ほぼ上限値となった。この水準は、新設ガス火力発電の固定費を5割も上回る水準だ。この約定価格が既存設備を含め、落札した電源(発電設備)に適用される。なお、2010年度末以前に建設された古い電源については約定価格から42%が控除される経過措置が設けられた。
ここまで高い水準の約定価格は海外でも例がなく、発電事業者にとっては「濡れ手で粟」の収入にほかならない。反面、容量拠出金を支払う側の小売電気事業者にとっては大変大きな負担になる。
経済産業省は発電事業者と小売事業者との間での既存の相対契約の見直しを促しているが、うまく機能する保証はない。卸電力取引所から主に電力を調達している小売電気事業者にとっては負担を転嫁できない。経産省は、容量市場が導入され、電源の供給が促進されることにより、新電力会社の調達先である卸電力市場の価格が安定すると説明しているが、その通りになるとは限らない。
――海外でも例がないという高値約定となった原因についてどう考えますか。

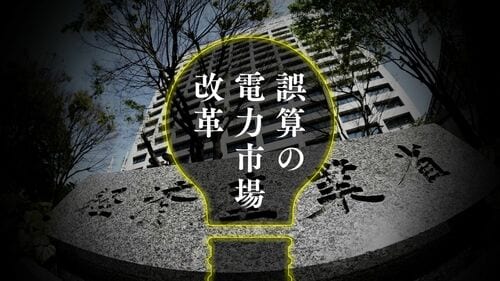



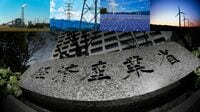





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら