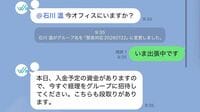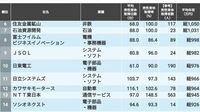性の話を「普通にできない」日本、先進国の性教育との差は何か ソウレッジ ・鶴田七瀬「包括的性教育」必要な訳

(写真:ソウレッジ提供)
また「子どもに性的な言葉や内容でからかわれ、いけないと思いつつ怒ってしまう」といった相談も多いという。これについては「性の話をして叱られることで、子どもがその話題をタブーだと感じてしまうのはよくありません。性の話が悪いのではなく、相手が嫌がることをやっているという点をきちんと注意すべきです」と答える。鶴田氏は、教員が子どもとの対話ができないことは、日本の性教育の大きな問題だと語る。これは家庭でも同様だ。
「『聞かれてもわからない』という不安があったとしても、それならやはり、親子で調べればいいのです。心配しているよ、何かあったら話してねと日頃から伝えておくこと。保護者と子どもの間で、性に関する話が普通にできることがいちばんの理想です」
大人のあり方だけでなく、教育の枠組みにも課題は多い。鶴田氏は「教員養成課程で性教育の科目を必修にしてほしいし、とにかく性教育の授業を行う回数を増やしてほしいですね。現行の3年に1回という規定はどう考えても少なすぎます」と指摘するが、明るい兆しも見えているという。
「私が活動を始めた2018年ごろに比べて、性教育の状況はかなりよくなっていると感じています。『自分でできるところからやっています』と言う教員の方も増えていて、講演内容もスッと理解されることが多くなりました」
また、冒頭で述べた「生命の安全教育」以外にも、国の方針に変化を感じるという施策を挙げた。
「21年の『経済財政運営と改革の基本方針』にも、『未来を担う子供の安心の確保のための環境づくり』として、性教育の話が盛り込まれました。こうなると教員の方も勉強し、対応する必要が出てきます。子どもにとっては先生たちの意識が変わることがいちばん重要なので、国としての指針にこうした単語が入るようになったことは大きな前進だと思います」
これらの流れのきっかけとして、鶴田氏は、17年の「#MeToo運動」で、自身も含め若い活動家が増えたことなどを挙げる。一人ひとりの活動によって社会変化のスピードが上がり、性教育への社会全体の理解度が高まっていると実感している。「行動してくれる人も増えています。これからもっとよくなるはず」と明るく語った。
(文:鈴木絢子、注記のない写真:Graphs / PIXTA)
東洋経済education × ICT編集部
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら