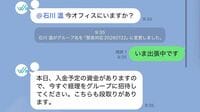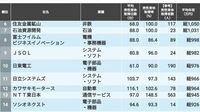性の話を「普通にできない」日本、先進国の性教育との差は何か ソウレッジ ・鶴田七瀬「包括的性教育」必要な訳
他者との健全な関係構築を学び「包括的性教育」へ
その後、鶴田氏はデンマークを拠点に、欧州の計4カ国を視察する留学を経験。そこでは性教育に限らず、日本との違いを感じる点が多くあった。
「日本は社会が決めたルールを守ることが重視されますが、私が訪ねた国では、自分たちでルールを作るところからトレーニングしていました。相手と自分の要望が違うときにどうするか、お互いにとっていいルールはどんなものか。こうしたことを自分で考えさせ、幼い頃から、他者と健全な関係を築く練習をするのです」
例えば、保育園で子ども同士がけんかをしたとする。日本なら先生が割って入って、一方に「ごめんね」と謝罪させ、一方に「いいよ」と許すよう促す。だがオランダでは、5歳の子どもにも「どうしたらいいか、自分たちで考えてきて」と時間を与えるという。子どもたちは互いに自分がどうしたいかを話し合い、2人で出した結論を先生に報告する。
他者と意見の相違があるとき、それをきちんと相手に伝えることは、多くの日本人にとって苦手なことだろう。だがそうした対人姿勢が、性教育以前の問題として好ましくない結果を生むと鶴田氏は語る。
「決められたルールを守るだけの受け身の姿勢は、男性が決めて女性が従うといった旧来のジェンダーロールにも影響していると思います。互いに納得できる関係性を構築するには、『ごめんね』『いいよ』以外の選択肢があることを、まず知ることが必要です」

一般社団法人ソウレッジ(Sowledge)代表
海外留学などを経て正しい性教育の必要性を感じ、2019年に同団体を設立。教員や保護者向けの研修や講演を行うほか、性の知識を身に付ける教材の開発・販売も。21年度Forbes「30 UNDER 30 JAPAN-日本発『世界を変える30歳未満』30人-」受賞。現在はソウレッジとして、緊急避妊薬の無償提供をきっかけに性知識の向上を目指すプロジェクトのクラウドファンディングを実施中
(写真:ソウレッジ提供)
性教育におけるこうした考え方は、すでに国際的に広まっている。単なる身体的知識だけを教えるのではなく、人権やジェンダー平等などを含めて幅広く学ぶ「包括的性教育」といわれるものだ。性教育先進国とされるオランダでもこの概念が浸透しており、性教育のスタートとして、愛情のあり方や自分の気持ちの伝え方など、まず内面的なことを学ぶ。