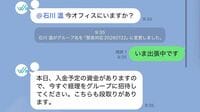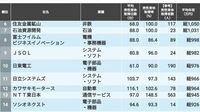性の話を「普通にできない」日本、先進国の性教育との差は何か ソウレッジ ・鶴田七瀬「包括的性教育」必要な訳
「オランダでは恋をしたときの感覚を『おなかでチョウが羽ばたいている』と表現することがあり、それに由来した性教育カリキュラムがあります。『ちょうちょパタパタ月間』と名付けられたそのワーク期間、子どもたちは図書館に行ったり親に質問したりして、性についての知識を自分たちで調べます。対象となる子どもは4歳から小学校低学年ぐらい。基本的な枠組みは先生が示しますが、性に関する疑問に直面したときに、自分たちで解決できるようになることが目的です」
男女の体の違いから始まり、年齢に応じ、性の多様性や健全な関係の保ち方についてなどを包括的に学ぶそうだ。また、鶴田氏はドラマなどのフィクションにも違いを感じたという。日本の恋愛ドラマでは、 何となく2人が折り重なっていくなど、あいまいに性描写が進みがちだ。そこには互いの意思確認もないし、避妊への配慮も描かれない。
「海外のドラマでは、性的同意を取ることもコンドームを着けることも、当たり前のこととして描かれます。日本では、女性にしとやかさが求められたり、『黙っているのがいい女』という風潮があったりしますね。和を貴ぶ社会でもあり、女性が嫌なことを嫌だと伝えることは難しい。でも妊娠の可能性など、何かあったときに負担が大きいのは女性です」
海外でも日本でも、「そんなときにそんなことを言ったら雰囲気が壊れる」など、性的同意に否定的な声もあるという。日本の恋愛ドラマを「いいムード」の手本と捉えればそうした考えにもなるだろう。だが鶴田氏は、性的同意の必要性を次のように説明する。
「私はこう思うけれど、あなたは?という問いかけがきちんとできて、それは違うんじゃない?と言うこともできる。まずこうした関係性を築くことが大切なのです」
性教育を考えるとき、最も重要なのは性の知識ではない。土台になるのは、相手を尊重し健全な人間関係を築こうとする、性以前のコミュニケーションの姿勢だ。
大人にもわからないことがある、子どもと一緒に調べよう
鶴田氏は学校の教員向けにも研修を行っているが、その際、「教える側と教えられる側」という構造をつくらないことを心がけているという。絶対の正解がほぼ存在しないこのテーマは、年齢や上下に関係なく、みんなで考え、教え合うものだと考えているからだ。
ソウレッジが制作した大人向けツールの1つに「ブレイクすごろく」がある。5歳の子どもが、成長過程でどんな性の悩みを持つかなどをゲーム形式にまとめたものだ。すごろくのマスには例えば、射精や月経を迎えて戸惑う子どもの様子が描かれる。「病気なのかな」「恥ずかしい」などと感じて大人に相談できず、誤った対処に走ってしまうリスクが具体的に示されているのだ。研修ではこれらを使って、教員自身にどうすべきかを考えてもらう。ゲームを通じて、子どもにとって性がいかに身近なものであるかに気づく教員も多いそうだ。
「研修では教員の方から、『自分も知らないことを聞かれたとき、どうしていいかわからない』『動揺してはぐらかしてしまう』と相談されることがよくあります。性教育は単に教えるか教わるかというものではないですし、先生にもわからないことがあると子どもに伝えていい。インターネットには危ないサイトもあるから、気をつけながら一緒に調べよう、というふうにしてあげるといいと思います」