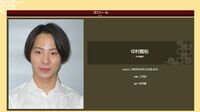71%がストレス低減「マインドフルネス」を学校で行う効果とは? 教員や学生のセルフケア支援で導入する学校も
現在、同社のマインドフルネス・プログラムには個人や企業だけでなく、教育現場からも声がかかるようになってきた。教員向けに小学校や高等学校で採用されたケース、子どもたち向けに学習塾で採用されたケースなどがある。そのほか、運動部の学生向けに活用する大学も複数ある。
明治学院大学では、2022年2~3月に対面プログラムと同社のオンラインプログラムを組み合わせたマインドフルネスの課外講座を予定している。同大学心理学部心理学科教授兼学生部長の宮本聡介氏は、導入の理由についてこう語る。
「私も実践しているので日頃から効果を体感していますが、マインドフルネスには自分の取り組みで心の問題を何とか整えられる要素があります。本学では心身の悩みを専任カウンセラーに相談できる学生相談センターを設けていますが、利用者も少なくありません。そんな学生たちにマインドフルネスを知ってもらうきっかけになればいいなと思って導入してみることにしました」
「非認知能力」を育むためにも心のトレーニングが必要
メンタル問題の懸念は一部の教育現場に限った話ではない。文部科学省の「令和2年度公立学校教職員の人事行政状況調査について」によると、教育職員の精神疾患による病気休職者数は、5180人。過去最多となった令和元年度の5478人からは減少したものの、依然高止まり状態である。
子どもの心の状態も見過ごせない。2020年9月にユニセフが発表した報告書「レポートカード16-子どもたちに影響する世界:先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か」では、日本の子どもたちの幸福度は38カ国中、総合順位で20位となった。
その内訳を見ると「身体的健康」は1位であるのに対し、「精神的幸福度」は37位。また、「スキル」は27位で、項目別には学力スキルが5位につけているものの、社会的スキル(すぐに友達ができると答えた15 歳の子どもの割合)は37位。この極端な結果を受け、橋本氏はこう述べる。
「子どもの幸福度には、対人コミュニケーションも関係するといわれますが、そういったソーシャルスキルが低いことがわかります。シックスセカンズ(※)によると、日本は非認知能力に当たるEQ(Emotional Intelligence Quotient)スコアも、調査対象国の中で最下位。つまり、自分や他人の感情を理解する資質・能力が欠如しているといえます」
※ EQの開発を専門とし、調査研究や情報発信を行う組織
実際、対人関係が影響するいじめや不登校は増えており、厚生労働省の「令和3年版自殺対策白書」によると、コロナ禍の20年における児童生徒の自殺者数は過去最多の499人となった。橋本氏には、何も悪くない子どもたちにシワ寄せがいっているように見えるという。
「心の健康はある意味基本的人権であり、国がそれを保障すべき。義務教育から、体育で体を鍛えるのと同様に心のトレーニングも行うべきではないでしょうか。そのセルフケアツールとして、自分や他人の感情に気づく力や共感力も高めることができるマインドフルネスは適しています。米国では公立の小中学校で実践が広がっていて、英国でも公立の小中学校で大々的な実証実験が始まっています。一方、日本はマインドフルネスという言葉の認知は広がりましたが、実践している人はまだまだ少なく遅れていると感じます」
「2カ月間のマインドフルネス」で小学生に起きた変化とは?
そこで、橋本氏は2021年5~11月に、小学校向けマインドフルネス・プログラムの実証実験に取り組んだ。「子どもたちがストレスとの付き合い方を学び自ら対処していくためにマインドフルネスは有効である」という仮説の下、協力してくれる小学校を募集。参加校の7校にはプログラムを無償提供した。