現役先生に聞いた「学校のICT活用」の進み具合 小・中・高校、大学の先生と塾関係者が語る実態
その活動の1つとなるSDGsに関連した「龍中ゴミ問題解決プロジェクト」では、マインクラフト(※1)も取り入れました。問題解決のためのプロトタイプを作成する場面では、理数的なものの見方や考え方を生かす生徒も出てきています。その生徒は、マップアプリケーションで、校舎の衛星画像を画面キャプチャーし、建物の寸法を計算してブロックの数を決めて、本物そっくりな龍谷中学校の校舎を組み上げました。こうした理数的なものの見方や発想を育むには、学びの場が必要であり、そこで学びのオーナーシップを生徒に渡すことが重要だと感じています。
※1 土や石などの立方体ブロックを自由に配置して、建物を構築したり、世界を冒険したりする、ものづくりゲーム。プログラミング教育などの教材にする教育向けエディションもある
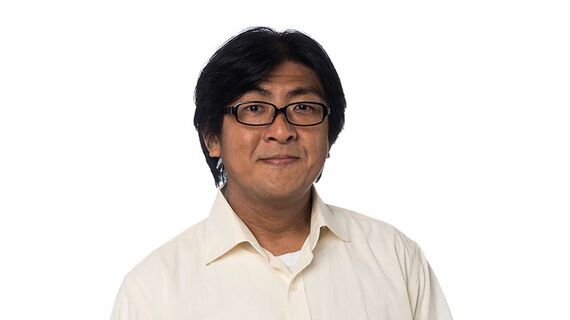
公立中学校勤務だった2013年ごろから教育へのテクノロジー導入の実践を重ねてきた。20年4月、iPadを使った教育にいち早く取り組んできた佐賀龍谷学園龍谷中学校・高等学校へ。「これまでの考え方や限界を打破して、子どもたちを中心に据えた教育を目指したい。VRやARなどのXRテクノロジーに興味あり」。Apple Distinguished Educator(画像提供:iTeachers)
岩居 大学の外国語の授業では、ロイロノート・スクール(※2)を使い、アクティブな授業に取り組んでいます。このサービスは、講義資料の配布だけでなく、音声や動画ファイルの配布、課題の提出などにも活用できます。ネイティブスピーカーの動画にアフレコさせたり、学生同士で短い会話のビデオを作成して提出するといった使い方もできます。また、ビデオ撮影をしながら音声認識で字幕をつけることができるサービスを使えば、モニターに映し出した自身の口の動きに注意しながら、自分の発音が正しく認識されるか、確認することもできます。
大学のICT活用度は、先生によってさまざまですが、コロナ禍でオンライン授業にスムーズに移行できた人は2割程度でしょう。中には、教材をオンラインで配布しただけで、学習している言葉を聞くことも、声に出すこともないという授業もあったようです。
※2 PC、タブレット、スマホで使える授業支援クラウド。教材の配布や、考えを書き出したり、画像を取り込んだカードをつなげてプレゼンテーション資料を作成できるほか、録音、動画撮影を使った音読のチェックなど、さまざまな活用実践例がある
小池 塾業界は、早くからeラーニングのドリルなどを導入し、子ども一人ひとりに合わせた個別最適化や、速読などでICT教材の利用に取り組んできました。が、その先のICT活用は進んでいません。ICTと相性のよい「創造性」を育てる教育は、受験や成績向上を目的とする塾に求められる領域ではないからです。
そのため、せっかく導入したICT機器を「どう活用するか」は業界共通の課題でした。しかし、コロナ禍で、Zoomなどを活用したオンライン授業をこぞって導入したことで、新たな方向性が見えています。これまでは遠くて塾に通えなかった子どもたちを受け入れることができ、コロナ対策にもなると、大手を中心にオンラインコースの設置も広がっています。






























