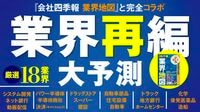DXのプロ採用「さいたまモデル」でGIGA加速 採用人数4人の枠に688人応募、その効果は?
今回のコロナ禍の中で細田氏は、これまでの同年代の子どもたちが同じ学びやに集い学ぶという学校のありようの“終わりの始まり”を感じたという。しかし、対面授業開始後に、子どもたちが喜ぶ様子を見て、その考えを改めた。

「リアルに子どもたちが集まって、ディスカッションしたり、一緒に体験したりする意義深さを今さらながらに痛感しました。その一方で、教育におけるICTの活用についてポテンシャルの高さも実感した。つまり、リアルとデジタルをどのように融合させていくのか。そうやって教育のパラダイムシフトを実現させていきたい。私はそんなアプローチもあると思っています」
とくにICTは、個別に最適化された学びにアプローチできる点を評価しているという。通常の授業だと、平均か少し上をターゲットに授業を行うが、それだと「吹きこぼし」が出てしまう。内容がわかっているから授業がつまらないという子どもと、わからなくて授業がつまらない子どもが出てしまうのだ。ICTを使うことによって、子ども一人ひとりの学びに合わせることが可能で、教員も個別にフィードバックできる時間が増え、つまずきも見えやすくなるという。
今、さいたま市教育委員会ではICTのほかにも、実社会にある課題と向き合い新しい価値を生み出す思考力を育成するために「STEAMS教育(STEAMにSportsを加えたさいたま市独自の取り組み)」やSDGs教育など21世紀型の学びも強化している。この中で、ICTをフル活用しながら社会とつながる協働的、探究的な学びを推進していく。
「これから学びのスタイルは確実に変わっていきます。情報端末がすべての子どもに行き渡れば、自宅での学びも変わっていくでしょう。今回のコロナ禍というピンチをただやり過ごすのではなく、最大限チャンスに変えていきたい。そのためにも“さいたまモデル”を早く構築して、多くの教育現場で活用できればと考えています」
(写真:梅谷秀司)
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら