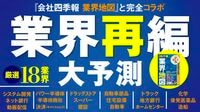DXのプロ採用「さいたまモデル」でGIGA加速 採用人数4人の枠に688人応募、その効果は?
「さまざまなICT活用法について、具体的なユースケースを共有することが大事だと考えています。これからの学校教育がどのように変わっていくのか。校長、教職員の皆さんに統一したイメージ、手段を持ってもらうためです。そのためにインフラ、セキュリティー、コンテンツなどカテゴリー別にそれぞれ教育委員会のスタッフ、教職員、DXスペシャリストが横連携しながら、全体のプロジェクトを動かしていくという仕組みをとっています」
細田氏をトップに「さいたま市GIGAスクール推進本部会」をつくり、DXスペシャリストを中心に教育委員会のスタッフと教職員らでプロジェクトチームを結成。さらにその下にインフラ、セキュリティー、コンテンツなど部門ごとに実行部隊となるワーキンググループを配置し、各学校のエバンジェリストが現場に落とし込んでいくという仕組みだ。同時に各学校でも、ICT教育推進部を必置とし、各エバンジェリストが動きやすい仕組みを導入した。
「想定以上にスムーズに動いています。現在、約10万3000人の全生徒に情報端末を配布できるメドは、来年の2021年2月。学校の高速大容量のネットワーク工事をしつつ、情報端末についてもベンダーの方々と折衝し、ようやく調達できるようになった状況です。生徒数も多いため、作業は本当に大変です。しかし、学びのパラダイムシフトが早まったという点では、大きなメリットがあります。日本のICT教育は諸外国と比べて周回遅れですが、今回それが一気に進むことになった。作業は大変ですが、期待感があります」
800超のデジタルコンテンツが集まった「スタディエッセンス」
その一方で、さいたま市教育委員会ではコロナ禍の休校中においても、独自の取り組みを行ってきた。それがデジタルコンテンツ「スタディエッセンス」だ。
「長く教育の世界にいますが、まさか学校が休校になるなんて想像したこともありませんでした。しかし、何としても子どもたちの学びを止めてはいけない。そこで教育委員会内の指導主事が、デジタルコンテンツを作ろうとなったのですが、やはり限界がある。ならば6000人の教職員たちの英知を結集させて作ればいいと思ったのです。もちろん当初は手探りの状態でしたが、突貫工事で何とか作り上げました。結果として、800を超えるコンテンツが集まりました」
ただ、課題もあった。コンテンツに優劣があったのはもとより、各家庭で子ども専用の情報端末を持っている率が30%以下だったのだ。ちょうどこの時期は、在宅勤務となる会社が増え、親も自宅でPCを使って仕事をする必要に迫られた。また、兄弟がいる家庭では複数の端末が必要になるため、「子ども専用」となると所有率が極端に低くなってしまうのだ。しかも、小学校低学年では情報端末を1人で使いこなすのが困難であるうえ、すべての児童が授業時間どおり、自宅で集中できるわけでもない。そんな学習の自律性も問われた。
「子どもが集中できる時間は10分から15分程度。子どもに負荷をかけさせないコンテンツと、そうでないコンテンツもあります。ただ、今回の『スタディエッセンス』の取り組みによって、改めてコンテンツの重要性に気づかされました。対面授業が始まった現在も、『スタディエッセンス』は予習・復習教材として使用されていますが、この取り組みで明確になった課題をGIGAスクール構想にも生かしていきたいと考えています」