アジア開発銀行による「原発建設への融資解禁」プロセスに重大な問題。核拡散や安全性、廃棄物など問題だらけで、日本企業の商機は乏しい
ADBのエネルギー政策文書の改訂案に対しては、世界中の市民社会から数多くの批判が寄せられている。ADBによる原発支援解禁に反対する要請書には、世界中から100団体・個人6101名の署名が集まり、ADBの総裁および12名の理事に送付された。
2025年8月にADBが開催したオンライン公聴会には、日本から福島原発事故の被害者団体連絡会のメンバーも参加し、福島原発事故の実態を直視し、福島でも公聴会を開催するよう働きかけた。しかし、原発の安全性についてはIAEAなどの国際基準に従うことになるとの一般的な回答のみで、福島での公聴会の開催要望は無視されたままである。
2021年に策定されたADBの現行のエネルギー政策文書では、原発導入における4つの障壁(核不拡散、廃棄物管理、安全性に関するリスク、極めて高い投資コスト)を根拠として、ADBは原発への支援を行わないとする方針を掲げている。筆者が所属する「環境・持続社会」研究センターを含む複数の環境NGOは、原発支援解禁にあたって、ADBが自ら掲げている4つの障壁をどのように克服するのかについて、ADB担当者に繰り返し質問したが、ADBからの回答は、論点のずれた不十分な回答だった。
例えば、SMRを導入した場合に軍事転用リスクが高まることが専門家などから指摘されている。そこで軍事転用リスクへの対応について質問したところ、ADBは「方針によって武器支援は禁止されている」と回答。発電用として納入された核燃料の軍事転用を防ぐための施策については回答がなく、説明責任を果たしているとは言えない。
また、日本を含め多くの国で高レベル放射性廃棄物の処分方法が決まっていない中、開発途上国での処分をどのように支援するのかという点について質問したところ、ADBは「IAEAが適切な技術指導を提供するだろう」と回答しており、公的融資機関としての責任を放棄しているかのような回答だった。
解禁は根本的な政策変更ではない?
ADBは、今回のエネルギー政策文書の改訂は「修正(amendments)と追加(additions)のみに限定される」と説明している。つまり、大きな方針転換ではないというのだ。しかしながら、その実態は根本的な方針転換にほかならない。
そこで筆者らが原発支援の解禁という方針の根本的な政策変更を行った理由について尋ねたところ、ADBから、「21年策定のエネルギー政策文書で原発導入に向けた技術支援を認めた一方で、原発支援を禁止する文言を入れたことは整合性が取れていなかった。原発支援を禁止する規定を削除したことは根本的な変更ではない」との回答があった。




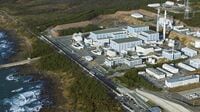



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら