ステイホームで、子どもたちへの虐待件数が増加している。子どもの「見守り」の機会が減る中、責任が問われるのは親だけなのか。

子どもの虐待を防ぐための解決策とは?写真はイメージです。(写真:maroke / PIXTA)
虐待はなぜ減らないのか
――2020年の子どもの虐待対応件数は、30年連続で過去最高を更新しました。なぜ虐待は減らないのでしょうか。
2000年代に入り、子育てのパラダイムシフトが起こった。それ以前は地域で子どもを育て、何かあれば近所の大人が面倒をみていた。私も幼い時に父に叱られ、家の外で泣いていたところを近所のおじさんに優しく声をかけてもらった覚えがある。
今はそうした地域社会が機能しなくなった。「子供の家」がある清瀬市では、そのことを強く感じる。清瀬市には都営住宅が多く、都内からあらゆる家庭が入居してくる。子どものいる家庭も多いが、住んでいた地域を離れて新たに清瀬にやってきたことになるため、近隣住民との関わりはない。引越してきた時点で、すでに地域社会から孤立したスタートになる。
――子どもを産んだら親がきちんと育てて当たり前、という自己責任論の風潮があると感じます。

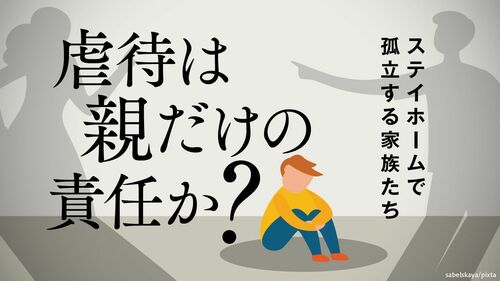































無料会員登録はこちら
ログインはこちら