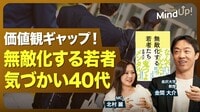「全国学力テスト」成績上位県の意外な共通点 小・中ともに石川、秋田、福井がトップに位置
1.「対話的な学び」を重視した授業
AとBは、普段の授業がどういう形で行われているかを示している。授業には講義型、問答型などさまざまな形があるが、中でも石川と秋田は「対話型」の授業が多いことがうかがえる。学習指導要領で重視されている「対話的な学び」である。
ただ正解を求めるのではなく、ハードルの高い課題に対し、自ら考え、グループや学級で話し合いながら試行錯誤を繰り返しつつ解決に迫るという授業である。例えば秋田ではそのような形の授業を「探究型授業」と呼び、県内の小学校・中学校で行っている。これらの取り組みは、難しい問題での無回答率の低さとも関係している。
2. 家庭学習への手厚いサポート
Cは家庭学習への指導がどこまで丁寧にされているかを示す。秋田は通塾率が極めて低く、それを補う意味で家庭学習への指導が丁寧に行われているのである。石川は通塾率がとくに低いわけではないが、それでも家庭学習の指導を手厚く行っている。石川が上位を占めた理由の一端がこのようなところからもうかがえる。
3. 教職員のチームワーク
Dは、教職員のチームワークの質を示唆している。教職員相互の同僚性の高さ、さらに授業研究など校内研修会での共同研究の質とも関わっていると推察できる。
1.「対話的な学び」を重視した授業
2. 家庭学習への手厚いサポート
3. 教職員のチームワーク
学力向上の取り組みは、さまざまな角度からさまざまな方法で行っていく必要がある。とはいえ、どの地域においても1.「対話的な学び」を重視した探究的な授業、2. 家庭学習への丁寧で手厚いサポート、3. それらの指導の質を高める先生方のチームワークが柱となっていくことは間違いない。
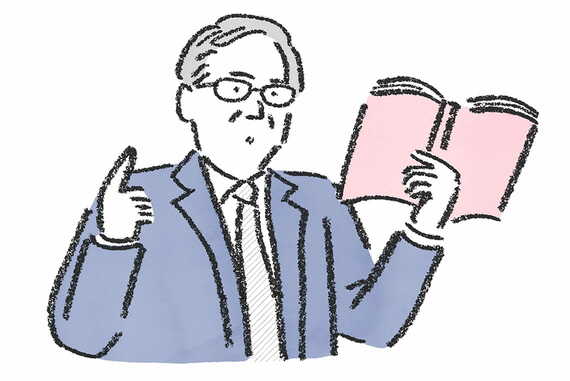
秋田大学大学院 教育学研究科 特別教授
東京未来大学特任教授。秋田大学名誉教授。教育研究者として、約40年にわたり小中高の授業の研究を行ってきた。専門は教育方法学、国語科教育学、授業研究。秋田県教育委員会・検証改善委員会委員長として12年間、秋田の学力について調査・提言を行ってきた。日本教育方法学会常任理事、全国大学国語教育学会理事、日本NIE学会理事。国語科教育専門サイト「国語授業の研究ノート」を運営
(注記のない写真はiStock)
執筆:秋田大学大学院 特別教授 阿部昇
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら