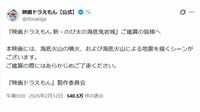助産師YouTuberシオリーヌ語る「性教育」のリアル 学習指導要領の「はどめ規定」とは、何なのか?
性教育について語るときに、たびたび言われる「寝た子を起こすな」という言葉がある。
これは、思春期の子どもに対して「わざわざ性教育で性行動について話して、寝た子を起こすな」という、考え方だ。主に性教育に反対する人たちが採用している理論でもある。しかし、この理論についても、すでに世界ではその理論は、必ずしも正しくないというエビデンスがそろい始めている。
「ユネスコが出している『国際セクシュアリティ教育ガイダンス』で世界的にスタンダードとされている性教育の内容を見ると、日本で行われている性教育はごく狭い範囲に限られていることを痛感します。こちらのガイダンスに基づいた性教育を、子どもたちに提供している国々では、高いリスクを伴う行為をする子どもたちが減少しているとデータにも表れています。性教育に反対するほうの意見として、『寝た子を起こすな』理論がありますが、大人は寝ていると信じたいだけで、子どもたちはネットやさまざまな媒体を通じて、すでにいろいろな情報を持っていることが多いのです。その情報は玉石混淆であり、その中で、自分の責任で意思決定をしなければいけないシチュエーションに子どもたちが直面していることに、大人は深く向き合わなければいけないと思います」
大貫さんがかつて勤務していた児童思春期病棟でも、子どもたちがSNSでコミュニケーションを取ることはもちろん、そこで出会った友達に会いに行きたいと言うのは日常茶飯事だったという。ネットにフィルターをかけて制限をかけるだけではなく、もうそれは避けて通れない現実として受け止め、「危険の予知や、人や情報をどう信頼するのかといった能力を、早急に身に付けさせるべきでしょう」と、大貫さんは続けた。
性教育は何歳から始めるべき?
性教育はいつから始めればいいかという問題は、親や教育者の間でよく話題に上るものだ。ユネスコの「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」では5歳からと記載されている。
「個人的には、性教育は何歳になったらスタートという区切りのあるものではないと思っています。子どもとコミュニケーションが図れるようになってきたら、性教育は始まるといっていいでしょう。例えば一緒にお風呂に入ったときに、プライベートゾーンを親がどう扱うのか。自分に対してどういう声かけをしてくるのか。また、『赤ちゃんはどうやってできるの?』など、性に関する質問が子どもから出たとき、親がどういう対応をするのかなど、親の一つひとつの言動がメッセージとなり、積み重ねられていくものが性教育だと思います」
また、男の子なのに泣くのはやめなさい、女の子だからピンクの服で……と、知らないうちに親がジェンダーバイアスをかけていないか、ということについても、意識を持ってほしいと話す。
「世の中には、さまざまなセクシャリティーやジェンダーの人がいて、そこに優劣はなく、一人ひとりの権利が同じように大切にされる必要があるということは、幼いうちから知っていく必要があります。その知識があれば自分自身を守ることができ、誰かを傷つけたり、誰かの選択肢を奪ったりすることもなくなるはずです。でも、実は大人たちにも無意識に刷り込まれたジェンダー感があることは、大きな課題です。個人的な話ですが、私も1回目の結婚の時には、すでにジェンダーについて発信を始めていたにもかかわらず、『妻とは』という意識にとらわれてしまい、義務感で毎日料理をしていました」と笑う大貫さん。当時はそれがとても辛かったそうだ。