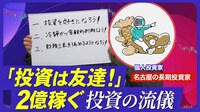プログラミング教育の基礎知識 現状と教育現場での課題

本稿では、プログラミング教育の概要を解説するとともに、現在の教育現場における状況や課題について考察していきます。
プログラミング教育とは
現代社会ではコンピューターを適切に活用することがますます重要になっています。2000年代以降になるとIT長者、ITベンチャーといった言葉も一般に広まり、プログラミングができればあらゆることをデジタル化させることができたり、さらにはそれが仕事になったりといったイメージを持つ人も多いでしょう。
ですが、学校教育におけるプログラミング教育は、アプリケーションなどを開発するための技術・知識を学ぶことだけが目的ではありません。
プログラミングという“題材”を通して、物事を分解して考える、あるいは順序立てて捉えるといった思考を身に付け、それによって各教科の学びを深めることがプログラミング教育のゴールです。
それぞれ新学習指導要領が開始となるタイミングで、小学校は2020年度からプログラミング教育が必修化され、中学校は21年度から技術・家庭科でプログラミング教育が拡充。高等学校では22年度から「情報I」で全員がプログラミングやデータベースの基礎などを学ぶことになります。
海外各国でも初等教育からプログラミング教育が導入されており、プログラミング教育を行うことで、これからの時代を担う子どもたちの可能性を広げることが期待されています。
必修化の目的
繰り返しになりますが、プログラミングの必修化は、プログラマーを育成することではありません。ほかの教科と同じように、子どもの可能性を発掘し、広げていくことが目的です。
加えて、プログラミングを学ぶことで、コンピューターの仕組みを理解して活用できるようになるなど「情報活用能力」を高めることも狙いの1つとして定められています。
文部科学省の方針と、小・中・高等学校におけるポイント
文科省は2019年、「小学校プログラミング教育に関する概要資料」を発表しました。
この資料によると、プログラミング教育では小・中・高等学校で共通のポイントと、それぞれで固有のポイントを掲げています。それぞれについて見ていきましょう。
小・中・高等学校共通のポイント
小・中・高等学校共通のポイントとして、文科省は次の2点を挙げています。
・情報活用能力を、言語能力と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位置づけ
・学校のICT環境整備とICTを活用した学習活動の充実に配慮
まずキーワードになるのが、「情報活用能力」です。
情報活用能力は、「各教科の学びを支える基盤」と捉えられており、具体的には以下の3つの要素が情報活用能力を構成する資質・能力として挙げられています。
・知識及び技能
・思考力、判断力、表現力等
・学びに向かう力、人間性等
また、すべての児童・生徒に1人1台のICT端末を配布するというGIGAスクール構想によって、学校のICT環境整備に拍車がかかっています。
小学校におけるポイント

小学校におけるプログラミング教育のポイントは、「プログラミング的思考」を育成することです。
プログラミング的思考とは、ある動きの組み合わせを考えて、どう組み合わせるべきなのか、どう改善すればより意図した動作につながるか、ということを論理的に考える力のことを指します。