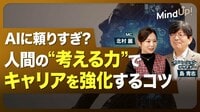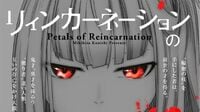「掛け算の順序問題」はやっぱり決着がつかない 5×4が正解のとき4×5がバツになる不思議
やはり、現場でも掛け算の概念を理解させることが重要との認識はあるようだ。そこで文部科学省に「式の順序だけで正誤を決めるのは避けたほうがいい?」と聞いてみると、次の返答があった。
「『こういう式に当てはめればいい』ということだけを教えると、思考の固定化にもつながりかねませんし、応用問題が解けないことも起こりえます。一方で、『1つ分の数』『いくつ分』といった言葉だけだとイメージしづらいので、具体的な日常生活と掛け算とのつながりを意識しながらご指導いただくことが大事だと思います」(文科省初等中等教育局教育課程課)
半世紀以上にわたって論争に決着がつかないだけあって、「掛け算の順序問題」は一筋縄ではいかないテーマだ。今回取り上げた以外にも、さまざまな歴史的な経緯や数学的な意味、教育上の目的が混在しており、検証するとそれぞれに正当性があることがわかる。
むしろ、順序の正否を問うべきかどうかにこだわるよりも、「小学校教育における掛け算の学び」という観点で、子どもの理解を促すにはどうすればいいかを優先すべきだろう。前出の数学者、遠山氏が1972年の朝日新聞の記事に接したときの所感にも、そうした思いが詰まっているように見える。
「これを読んでまず感じたことは、テストはなんのためにやるのか、という疑問であった。そして、この論争に参加しているほとんどすべて人びとが(原文ママ)、テストの意味について考えていないらしいということであった。(中略)テストをやってバツをもらった子どもは、『おまえはできなかった。だから、そう思え』ということだけで放り出される。バツになった理由を子どもが納得できた場合には、まだよい。しかし、子どもがなぜバツをつけられたのか納得できなかったときには、先生に対して不信感が生まれるだろうし、算数がきらいになってしまうこともあるだろう」
半世紀近く前に発せられたこのメッセージには、子どもに教える際にとるべきスタンスがすでに示されているといえよう。文科省の「具体的な日常生活と掛け算とのつながりを意識しながらご指導いただくことが大事」という提言と併せて、掛け算を子どもに教えるときに意識すべきポイントといえるのではないか。
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら