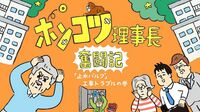「学習空間デザイン」議論必要なこれだけの理由 先駆けて検討重ねた長野県の設計構想は必見

(提供:オカムラ 写真:Nacása & Partners)
「ハードとソフト」のリンクが課題
こうした学習空間を実現するうえで、赤松氏は次のような問題を指摘する。
「当然、プロジェクターなどICT機器が使いやすい環境がいいですが、機器類は日々進化し続けているので、それにどう対応していくかは課題。現時点では機器交換や配線類の交換のしやすさなども考慮して設計する必要があります。
また、『ハードとソフト』、つまり建物と使う人をつなぐことが非常に重要。学校は、設計者が教育委員会・先生・地域・児童生徒と議論を重ねたうえで設計しますが、委託される業務自体は完成して引き渡しまでなので、実際に使う人たちに設計経緯やよりよい使い方を伝える機会がなかなかつくれない現状があります。
そこで、私たちは千葉市立美浜打瀬小学校が使われ始めた後、設計経緯やオープンスクールという学校施設のあり方、そのメリットをワークショップ形式で先生方にお話しし、ワークスペースの活用方法を議論しました。こういう機会があれば先生は積極的に考えてくれます。大切なのは、建築が完成した後、設計者と先生が一緒になって空間の活用方法を考えていける体制づくりです」
このほか、同報告書では、多様な学びを促進して地域と学校が共創する「地域連携協働室」の必要性や、今まで見過ごされてきた「生活空間」としての快適性なども強調されている。また、学校は公共建築であり簡単には建て替えられないため、長期的な視点も重視する。
「今後、子どもが減っていき、教室が余ったら間仕切りを取り大きな空間にしてもいいし、地域の高齢者が使えるようにしてもいい。少子高齢化による行政の財政縮小の観点からも、学校機能以外での利用も可能な設計をすることが大事になります。基本的に地域の気候風土に合わせ、通風や採光、断熱、耐震などを担保した快適な場所になっていれば、空間の応用は利きます」(赤松氏)
村澤氏は「文科省が推進する個別最適な学びと協働的な学びの実現には、『ツールの進化によるICT化』だけでなく、多様な活動を誘発する『物理的な環境としての空間』が必須。ここは本来セットで議論していくべきで、それが全国でできたら学校はもっと面白くなっていくと思います」と、期待する。
「県知事も同報告書を大事にしたいと発言しており、現在、実現に向けて各学校の築年数やコストなども含めさまざまな観点から検討が進んでいる」(村澤氏)という。新時代の学びや学習空間のあり方について多くの示唆を与えてくれるこの報告書は、同県教委のホームページで見ることができる。
(文:編集チーム 佐藤ちひろ、スケッチの出所:「長野県スクールデザイン2020~これからの学びにふさわしい施設づくり~」)
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら