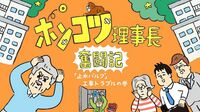「学習空間デザイン」議論必要なこれだけの理由 先駆けて検討重ねた長野県の設計構想は必見
こうした中、新型コロナ禍の影響でICT化が広がり、改めて学校施設を見直す流れになった。そもそも学校は全国的に老朽化が激しく、建て替えに当たっては少子高齢化に伴う自治体の財政問題や地域連携などの視点に立つ必要性も以前から指摘されており、「これらの複合的な理由から学校施設の見直しの議論が進み始めている」と赤松氏は言う。
とはいえ、文科省の「新しい時代の学校施設検討部会」は2021年2月に第1回の会合が開催されたばかりで、本格的な議論はこれからだ。そこで今回は、赤松氏が委員長を務めた長野県の「県立学校学習空間デザイン検討委員会」がまとめた最終報告書「長野県スクールデザイン2020~これからの学びにふさわしい施設づくり~」で提案された学習空間の内容を紹介したい。
新しい学びに必要な空間設計とは?

長野県教育委員会事務局 高校改革推進役。4高校で教諭を務め、長野県教委事務局指導主事、軽井沢高校校長、県教委事務局高校教育課長などを経て、上田高校校長、県高校長会長。SGHを核とした学校改革に取り組み、2018年3月定年退職、同年4月から現職。中央教育審議会「新しい時代の高等学校教育の在り方WG」委員など
(提供:長野県教育委員会)
長野県教育委員会がいち早く18年に学習空間の検討を始めた背景について、同検討委員会の委員も務めた同教委事務局 高校改革推進役の内堀繁利氏はこう語る。
「長野県は今、学校や教員が主導する『教育』から子どもたち主体の『学び』に転換しようとしています。すべての教科・授業で探究的な学びを取り入れ、ICTも必須の文房具として位置づけていく。3人に1台の端末整備と普通教室を中心としたWi-Fi環境の整備を20年度末までに完了しており、21年度からBYODも進めます。高校改革では、こうした学びの改革と新たな学校づくりを一体的に推進することとしていますが、そうなると当然『学習空間』という捉え方が重要になる。そこで、検討委員会が設置されたのです」
同教委事務局 高校教育課施設係 担当係長の村澤史浩氏は、これは今までになかった取り組みだと話す。

長野県教育委員会事務局 高校教育課施設係 担当係長。建築職として長野県入庁。2017年度から現職。県立学校の施設整備等を担当。「県立学校学習空間デザイン検討委員会」では、事務局担当者として立ち上げから最終報告「長野県スクールデザイン2020」まで携わる。同報告内容を県立学校で実現するよう、庁内での検討を推進中
(提供:長野県教育委員会)
「全国的に学校は老朽化しており、その修繕などは当県でも取り組んでいますが、空間として学校がどうあるべきかという議論はされてきませんでした。そこについて、赤松先生をはじめ各界の専門家に集まっていただき、県立学校全体として総合的に検討できたのは本当に画期的なことです」