子どもの「人生の選択肢」無意識に狭まる大問題 地方の限界を打開する「現代版寺子屋」の正体
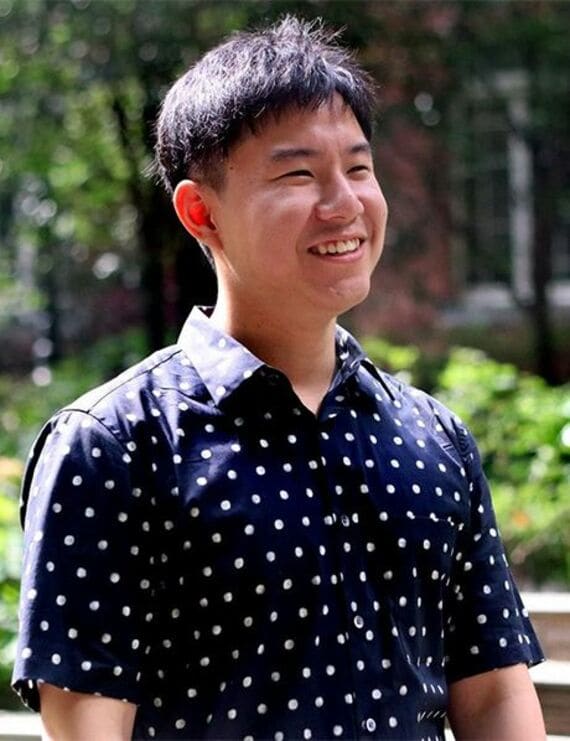
学校の外からビジネス・仕組みづくりの観点で教育に関わることを決意し、4年間デロイトトーマツコンサルティング合同会社で経営コンサルタントとして勤務。大手電機メーカーの全社改革や新規事業開発等のコンサルティング経験を経て、2019年に札幌へUターン。tomonasu合同会社を創業
(写真:嶋本氏提供)
「寺子屋長という仕事は、地域おこし協力隊や青年海外協力隊のセカンドキャリアになるかもしれません。地方で宿泊施設を経営している方が副業として寺子屋を開くなど、運営規模や運営形態は地域ごとに異なると考えています」
あしたの寺子屋のビジネスモデルとしては、フランチャイズ形式と言うとわかりやすいが、「同じ目的の下、進化を続けるティール組織を目指す」(嶋本氏)という。2021年4月には日本各地に寺子屋が誕生する予定で、4月以降も第2弾となる研修を行い7月にはさらに多くの寺子屋がスタートする見込み。5〜10年間で1000カ所の寺子屋設置を目指している。
「実は、私たちと同じ志を持って、すでに活動をしている方が全国にいらっしゃいます。神奈川県藤沢市のおでん屋さんの一角で行っている寺子屋の陽向舎(ひなたや)や、北海道札幌市でゲストハウスと併設し、地域の大人や観光客と学ぶグローカル志向の寺子屋のアドベンチャークラブ札幌などがあります。こうした、すでに活動されている方にも声をかけながら、あしたの寺子屋に参画していただき、ノウハウの提供やアドバイスをお願いする予定です」
どこに暮らしていても、新しい世界や周囲にはいない生き方をする大人と出合える場所。そんな子どもたちの第3の居場所が、地方と都市の教育格差を埋めることができるのか、注目したい。
(注記のない写真はiStock)
関連記事
「都市vs地方」生まれによる教育格差の深刻度 ベストと思う進路でも出身地域で差がある理由
世界30カ国「英語で交流授業」する先生が凄い 都市と地方の教育格差ICTで縮めるのは可能か
制作:東洋経済education × ICT編集チーム
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら






























